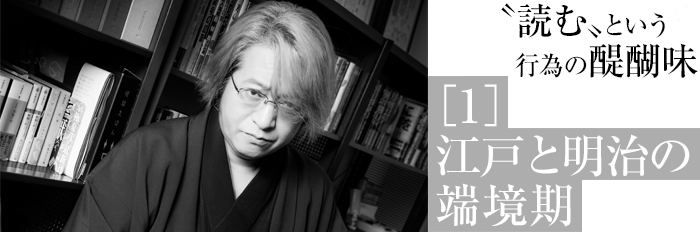
──今回の舞台になっているのは明治二十五(一八九二)年から二十六年にかけてですが、最初のほうで弔堂の主人がこんなことをいっています。
《書き記してあるいんふぉるめーしょんにだけ価値があると思うなら、本など要りはしないのです。……本は内容に価値があるのではなく、読むと云う行いに因って、読む人の中に何かが立ち上がる──そちらの方に価値があるのでございます》
電子書籍という新たな本の形態が出てきている現在、この言葉は本というもの、あるいは本を読むことの本質とは何かを改めて考えさせます。
本に書かれている情報、内容だけが大事なんだというようなことをおっしゃる方は昔からいます。一方で、本を骨董的なもの、あるいはコレクターズアイテムとして扱う人もいる。ぼくは個人的に、どっちもNGなんです。
電子書籍は今でこそ普通になりましたけど、ちょっと前までは珍しかったせいか、テキストを配信するだけで金が取れるんだと勘違いする愚かな作り手も多かったですね。価値があるのはテキスト=情報であって、書籍に価値があるのではない、ということですよ。でも、それは大きな錯誤です。売れるのは小説そのものじゃなくて商品としての本です。本を売るために編集者や出版社がどれだけ努力しているのか。間違いを減らすために校閲の人が一所懸命ゲラを読む、読みやすい書体を選ぶ、めくりやすい紙を選ぶ、手に取ってもらえるような装幀をする……そうやって商品としての本を作っているから読んでもらえるのであって、むき出しのテキスト・データがそのままあっても、読んでもらえないですよ。
一方で、ガラスケースに稀覯本を並べて、温度・湿度管理を徹底して、取りだす時には手袋をするようなコレクターもいるんですね。家族は困るわけです。お父さん寒いよ、暖房入れてよと(笑)。それも違う。本はあくまでも読んでなんぼ、のもんです。たとえ百万円だろうが十円だろうが、買っちゃったら自分の本だし、なら読もうよと。読まない限りその本には何の価値もない。
内容や情報にだけ価値があるわけではないんだけど、物として捉えるだけもいけないんだと思う。じゃあ、本とは何なのかということになるんですけど。結局、「読みたくなる/読む」ことこそが大事なんですよね。情報が大事なんじゃなくて、情報から何を酌み取るのかが大事なんであって、そのためには読むという行為が欠かせない。読者なくしては成り立たないものです。本は、「読んでもらうため」の装置なんです。電子だろうが手書きの写本だろうがそこは変わりがない。出版社をはじめ多くのスタッフが関わることでその装置はでき上がってる。だから本当は、編集から校正、印刷、製本に至るまで、本を作るのに携わった人全員の名前を映画のスタッフロールみたいにカバーに並べたいくらいです。ちょっと無理なので、代表としてぼくの名前になってますけど、「ぼくの本」という意識はない。ぼくは本作りの一スタッフにすぎません。
現在の本を取り巻くそういう仕組みは、一朝一夕にでき上がったものではないんだけど、ずっとそうだったわけでもないですね。出版社が本を作り、取次が日本全国に配本し、発売日には書店さんがいっせーのせーで売るのは、当たり前のようなんだけど、このシステムができたのはさほど古いことではなくて、江戸期の流通の仕組みから転換したのが、ちょうどこの明治の中頃なんです。今、電子環境の進歩普及に則して書籍のあり方が大きく変わりつつあるわけだけれど、明治期にも大きな転換があったわけです。本を「買う」こと、それに伴って「読む」という行為自体の意味が変わったという点においては、その時の方が変化は大きかったようにも思います。
──この明治二十六年に、出版法が成立しています。出版にとって大きな端境期だったと思いますが、翌年には日清戦争が始まり日本社会全体が大きく変わっていく。江戸と明治が交代していく微妙な時期でもありますね。
まさにそうなんですね。戦争みたいな国家的大事が起こると、経済の仕組みも大きく変わるし。技術革新も起きる。そうなれば、社会も文化も影響を受ける。一人一人の懐事情も大きく変わるわけですし。まあ、今の状況と似ているのかもしれません。最初は、現代と明治二十年代との類似点なんてまったく眼中になかったんですけど、書き進めると結構近い気がしてくる。いや、ただ「人はそんなに進歩しないもんだ」ということなんでしょうけど。