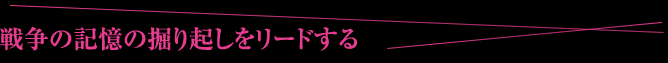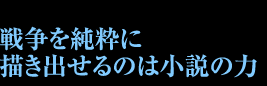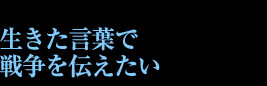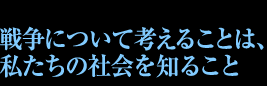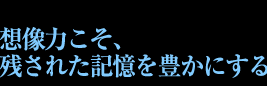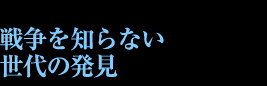|
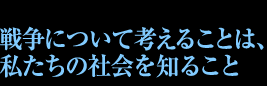 |
| 二〇世紀を「戦争の世紀」と呼ぶ人たちもいますが、残念ながら二一世紀の現在も、テロなどを含め様々なかたちで戦争はおこり続けています。しかし私たちは日々のニュースのなかで伝えられる戦争を、自分たちの生きる社会とは遠い世界の出来事として受
け取っていないでしょうか。つまり戦争に対するイメージや、戦争の存在そのものが私たちのなかで希薄になっている。これは、日本の社会が平和であることの裏返しかもしれません。ではその平和は、どのような歴史や世界の状況によって成立してきたのでしょう。今の社会を考える上でも、文学が明治以降、戦争をどう描いてきたか、そして現在どう描いているかを知ることは、大きな意味を持つと考えています。 |
|
|
 |
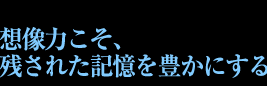 |
| 戦争を直接体験した世代の多くが歴史の表舞台から退き、彼ら彼女らの証言も覚束なくなってきた。残されたのは記憶だけである。わたしは思う。いまや戦争をめぐる言説の最大の問題は記憶の欠如などではなく、むしろその過剰さではないか、と。ここで文学の出番だ。なぜなら、先行世代の記憶を豊かにするのも貧しくするのも、結局は想像力をおいて他にないからだ。現代人が直面する〝記憶をめぐる戦争〟のただ中で、この記念碑的なアンソロジーが刊行されたことを、心より慶びたい。 |
|