
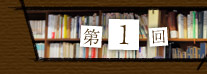 |
 |
 |
 |
 |

【第5回】
――エピローグで『ハムレット』の一節、「人殺しの罪には、みずから語る舌はないが、因果の不思議、何かが代わりに話してくれる」が引用されます。
桜庭 殺人を犯しても捕まっていない人は世の中に存在するはずです。殺人者をずっと書いてきて気になっている部分なのですが、殺人を犯した者はまったく他人に気づかれずに暮らしていけるのか、それとも何か変化がもたらされるのか。私はその人のどこかが、何かが必ず変わると思っています。夫婦仲も良く、娘からも尊敬されている解はその後しわしわに老けてしまいます。ある「欠如」が顔や姿に表れてしまう。捕まえてもらえないまま、一人でどこまでも続く廊下を歩いていかなければならない。誰も彼を捕まえることができない。彼が何をしたかもわからない。こんな孤独があるでしょうか。 ――エピローグでは、二十歳になった解の娘が語り手になりますね。 桜庭 エピローグを付けるなら娘に語らせようと考えていました。彼女は物語のいちばん外側にいる人物です。中心人物から始まったプロローグに対応させる形で、いちばん外側にいる部外者の娘が語ることで、物語にコーティングが施され、何重にもなった話が完結すると思いました。 ――さらにその外側には、「作者」がいるのではないでしょうか。小説家はテキストの中で自由に殺人や犯罪を犯すことができる特権的な存在です。作者は登場人物の死にいかに責任をとるのか。その点についてはどのようにお考えでしょうか。 桜庭 なぜ殺人者を書いてきたんですかと聞かれることがあります。その度になぜだろうと考えますが、なかなかうまく答えることができません。ドラマ性を高めるためとか、現代における死の意味について考えるためとか、考え続けてきたわけですけれど、殺人者とはもしかしたら作者自身なのかもしれないと思います。作中で毎度毎度、殺人を犯しているのは作者の自分自身かもしれない、と。『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』を書いた後、悪人として書いたお父さんにいちばん感情移入ができたと複数の人からいわれました。自分の中に殺しても殺しても死なない存在がずっとあって、ばらばら死体にしたとしても、また蘇ってくる。うまく向こう側に送りたい気持ちがあるんです。それでも消えない。それどころか、どんどん向こうの免疫機能が向上して強くなり、殺虫剤の効かない蚊みたいになっていく。
|
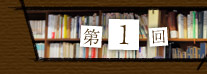 |
 |
 |
 |
 |
