
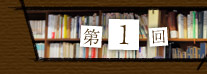 |
 |
 |
 |
 |

【第2回】
――冒頭部分、プロローグの「II 二〇〇九年十二月」で、死体をばらばらにする情景が描写されます。ジェンダーを示す自称詞を外して、犯人と被害者が誰なのか推定できない方法が採用されていますね。
桜庭 サスペンスの手法の一つとして、時間の組み換えをやってみたかったし、誰が殺されたのか考えながら読んでもらうことで、人間ドラマの側面が強調されると思いました。私はミステリ好きですが、謎解きそのものが目的ではなく、謎の意味を通して人間とは何かという本質的な謎解きがなされる、そのようなドラマを書くためにミステリの方法を使う作品が好きです。具体的にいえば、欧米の女性作家カトリーヌ・アルレーやパトリシア・ハイスミスが書くサスペンス。映画にもなったボアロー&ナルスジャックの『悪魔のような女』のような、どちらが騙しているのかわからないようなスリリングな、ドラマを盛りあげる手法として謎があるようなサスペンスを目指しました。 ――凶器の鉞の扱い方など、桜庭さんならではだと思いました。鉞を下北半島の形状にイメージ連鎖させていくプロセスは見事です。 桜庭 辻原登さんの『東京大学で世界文学を学ぶ』の中で『ボヴァリー夫人』が取りあげられていています。ボヴァリー夫人が読んでいる本の中に犬が出てきて、その後、実際に犬を飼うことになり、ボヴァリー夫人が亡くなる時に犬の吠え声が聞こえる、との指摘がありました。本の中の犬、本の中から現実にやって来る犬、夫人が自殺する瞬間の犬の鳴き声。犬が象徴している裏テーマがあるわけです。日本の小説の中での使用例は少ないかもしれませんが、私もそういうやり方が好きです。『私の男』で急に幽霊が出てくるシーンに異議を唱えられて、これを認めてしまっては自分が信じてきた文学を否定することになると論評されたことがありました。その方が取り組んでこられた文学があるわけで、それはそれでよくわかるし、桜庭一樹の小説を否定されても腹が立つことはないけれど、私の一人称小説では、霊感のある人の語り手には幽霊は見えるし、霊感のない人にはまったく見えない、そういう書き方になるんです。 ――欧米小説的な技巧と日本の土着的な風土の融合こそが、桜庭さんの新しさなのかもしれないですね。 桜庭 日本の田舎の土着的な風景に加え、私が読んできた外国文学、特にラテンアメリカやアイルランドが好きなので、周縁的な外国の土着と日本の土着が混ざる所に、私の小説のエッセンスはあるのかもしれません。今回、下敷きにしたのが、ダブリン出身の女性作家マーガレット・マッツァンティーニが書いた『動かないで』を原作に、夫のセルジオ・カステリットが監督・主演したイタリア映画『赤いアモーレ』です。 ――桜庭さんの小説ではおなじみの、章ごとに語り手が切り替わる技法が踏襲されています。しかし、違いもあります。たとえば『少女七竃と七人の可愛そうな大人』(06年)や『私の男』と異なるのは、同一シーンが違う人物によって語り直される点です。各章が微妙に重なる形で、物語全体が一つの集合体になっています。
――今回、桜庭さんは「経済問題」を導入されました。沙漠は時給八百五十円のラーメン屋で働くワーキングプアで、この十年ぐらいの日本の社会状況を背負ったヒロインです。桜庭さんが非常に具体的な形で経済にアプローチされている点が驚きでした。 桜庭 これまでも作品の中に現代的なテーマを組みこもうと考えてきました。お金をテーマにしたのは、自分の年齢や環境の変化が関わっているかもしれません。直木賞をいただいた後に収入が増えて、お金について考える機会が増えました。私にはオタク的な性向があるので、収入がなければ困るけれど、ある程度以上の収入があっても浪費することはありません。 ――沙漠は、美容整形の広告を見て十五万円を消費者金融から借り整形手術を受けます。整形を重ねる沙漠は十五万円を出発点に、借金を徐々に膨らませていき、闇金に手を染めるようになります。沙漠の根底には自己認証の問題があると思います。砂漠には「あるべき自分」のイメージがあり、全身整形を通してそのイメージに近づこうとします。最終的に、自分の体を売ってお金を得ることに躊躇しない人間にまで身を堕とします。 桜庭 『私の男』を書いたときに、ヒロイン腐野花の父親の淳悟をものすごくだらしなくてだめなお父さんとして書くことは簡単だと思ったんです。娘を美しく書き、父親をだめ人間として書くことは簡単だけれど、この父親を魅力的に書くと、嫌だけれど魅力的な話になると思いました。だらしなくてだめな女性を糾弾するように書くのではなく、魅力的に書くとどうなるだろうと考えました。沙漠は淳悟の男女逆バージョンといえます。 ――タイトルにある「ばらばら死体」は、一義的には作中で行われるばらばら殺人事件を指しますが、「まとまりがなく、散らばっている様子」を意味する「ばらばら」は、現代日本を象徴する言葉として適切だと思いました。ばらばらは、生活感や倫理が崩壊してしまった沙漠そのものを表す言葉でもあります。主体の欠落した沙漠のばらばら感は、同時代の読者に共有可能な感覚だと思いました。 桜庭 確かにいまの日本を考えると、「首切り」を超えて、手足も胴体もばらばらにされている感じかもしれない。『私の男』を書いていた頃は、「切り花」のような感じだったけれど、それより数段階進んで、全身ばらばらになってしまっている感じはありますね。映画『フォレスト・ガンプ』は、アメリカの歴史をなぞった作品だといわれています。主人公のフォレストはアメリカの歴史の明るい部分を象徴していて、フォレストの彼女のジェニーは負の部分を背負わされています。ジェニーは幼少期には親の虐待に遭い、大人になってからはヒッピーカルチャーに染まって薬物に依存する生活を送り、最後は亡くなってしまいます。泪亭の大家が「いまや、この国じたいが法律改正前の多重債務者みたいだ」と語りますが、この国の悪い部分のすべてを象徴する人として沙漠を書いたように思います。 |
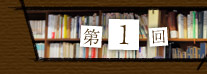 |
 |
 |
 |
 |

 桜庭 たとえば、ヒロインの沙漠がずっと語り続ける形にしてしまうと、主観が強調されすぎると思ったんです。語り手を換えていくことによってサスペンス的なドラマが見えてきますし、お金をテーマにしたので、いろんな人を登場させて同じシーンを語らせることによって、お金についての考え方の違いが浮き立つと思いました。登場人物全員に「お金って何なんだろう?」という問いを議論させかったんです。
桜庭 たとえば、ヒロインの沙漠がずっと語り続ける形にしてしまうと、主観が強調されすぎると思ったんです。語り手を換えていくことによってサスペンス的なドラマが見えてきますし、お金をテーマにしたので、いろんな人を登場させて同じシーンを語らせることによって、お金についての考え方の違いが浮き立つと思いました。登場人物全員に「お金って何なんだろう?」という問いを議論させかったんです。