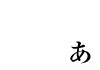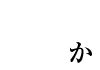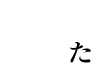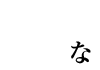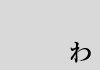1789年、教会所有の国有化と競売が決定され、それを担保にフランス革命政府が発行した新紙幣。封建権力の所有する土地をブルジョワジーに解放する役割を果たした。また他方で、すでに流通していた貨幣を駆逐してしまい、深刻なインフレを引き起こしもした。教会財産が没収されたことにより、フランス教会はローマ法王へ税を収めることが出来なくなる。それにより、当初から「人権宣言」を神に背くものとして認めていなかった当時の法王・ピオ6世と革命政府は深刻に対立することになった。
アナカルシス・クローツ
本名ジャン・バプティスト・”アナカルシス”・クローツ。プロイセン領の裕福な貴族に生まれる。1776年、パリにおいてディドロの「百科全書」の編纂に参加し、のちにフランスに亡命。1790年に行われたシャン=ド=マルスの連盟祭にはヨーロッパのみならずアジア人をも含む一団に民族衣装を纏わせて現れ、連盟祭への参加を議長ラメットに要請した「人類の代弁者」。
彼の主張である国家を超えた「人類主権」は革命初期には受け入れられ、プロイセン国籍を持ちながらも国民公会の議員となった。またエベールの下で非キリスト教化活動を推進した。
国家を超えた革命思想は非現実的であり、また恐怖政治の激化と共にナショナリズムに傾倒してゆく革命政府からは、やがて排斥の対象とされた。ロベスピエールによるエベール派の処断の際、ともに断頭台の露と消えている。
1775年、アメリカ東部13の植民地と、その宗主国イギリスとの間に起こった戦争。フランスはアメリカ側について参戦し、その独立を助けた。当時財政破綻寸前だったフランスはこの戦いで莫大な出費を強いられた。貴族・ラ・ファイエットは海を渡り義勇兵として参戦、ベンジャミン・フランクリンとの親交を得た。この経験がのちのフランス国民議会で採択された人権宣言などに影響を与えている。
アンシャン・レジーム旧体制、古い体制を指すフランス語。国王を頂点に聖職者の第一身分、貴族階級の第二身分、平民の第三身分と、ヒエラルキー構造になった身分制度のことを指す。
ヴァンデの暴動諸外国による対仏包囲網が出来上がりつつある中、国民公会はその外圧をはねのけようと、三十万徴兵令を決議した。フランス全土では兵役対象者をくじ引きで選ぶこととなった。が、革命により恩恵を受けている実感が薄い農村部の国民らはこれに激しく反発。ヴァンデ県では立会人の聖職者が惨殺され、そのまま大規模な反乱となった。反乱軍は「ヴァンデ軍」となり、その指導者には元貴族や軍人もいた。彼らは革命と共和国の打倒を叫び、宣誓拒否僧を支持した。つまり、反革命の反乱である。 元来この地方はカトリックへの信仰心が篤い地域であり、聖職者民事基本法に不満を持つ民衆が多かったことも原因とされている。
牡牛の目の間ヴェルサイユ宮殿の中にある王の居室。1701年・ルイ14世の治世に、控えの間と寝室を統合して作られた広間。牡牛の目の形のような鏡と窓があるためにこのような呼名がついた。
オランプ・ドゥ・グージュフランス革命時に女性の権利を求めて運動した、強硬な女権論者。大変な美女だったと伝えられており、料理人の夫と死別してからは富裕層の愛人となって蓄財し、文筆家として名を挙げるようになる。幼少期に充実した教育を受けなかったために口述筆記による執筆だったが、政治的なパンフレットから戯曲まで、さまざまなジャンルで活躍した。「人権宣言」に対抗して発表された「女性と女性市民の権利宣言」では「女性は処刑台に登る権利を持っている。それゆえ、同様に演壇に登る権利も持っている」と述べた。
暴動対策のためにジャコバン派の提案で設立された、特別刑事裁判所。ジャコバン派は吏員の任命を国民公会で行うと宣言し、ここで三権分立の精神がないがしろにされることとなる。場所はシテ島の旧王宮・コンシェルジェリ。首席判事から市民の陪審員にいたるまで全てを国民公会の指名となる。
髪粉主にジャガイモの粉や小麦粉などを原料にした、髪に振りかける白い粉。普段から髪粉を振りかけて髪を真っ白に保っていれば、地毛が白髪になった際でも老化に気づかれることがないとされ、貴族や富裕層の間で流行した。髪粉を振りかける作業は大変に手間がかかり、またパンの原材料ともなる小麦粉を大量に使用するため、革命の進行とともに廃れた。
カルチエ・ラタンパリ5区、6区にまたがる学生街。ソルボンヌ大学をはじめグランド・ゼコール(高等専門学校)やエコール・ノルマル(高等師範学校)など古くからの教育機関が集まる地域。「ラタン」はラテン語のことで、高い教育を受けた学生たちが集う場所、というのが語源である。
カルマニョール服
革命時のサン・キュロットの典型的な服装とされた短い丈のジャケット。名の由来はイタリア北西部・ピエモンテ州にあるカルマニョーラという都市の名から。そこで暮らす小作農たちが着ていた服が南フランスに伝播し、サン・キュロットらの間で大流行した。
また同名の「La
Carmagnole」という革命歌もある(作者不詳)。こちらは国王一家、特にマリー・アントワネットを痛烈に批判した歌詞となっており、サン・キュロットらはこの曲を歌いながら大いに踊ったと伝えられている。
当時高名だった医師ジョゼフ・ギヨタン、ルイ16世の侍医ルイ、そして死刑執行人サンソンによって協議、開発された斬首機械。それまでのフランスでは身分によって死刑の方法が異なり、苦しみが少なく一瞬で死ねる斬首刑は「高貴な処刑方法」と されていた。が、革命が進行するにつれ人権意識が高まり、庶民に対してのみ苦痛の伴う八つ裂きや車裂きの刑などを行うのは不当、処刑は斬首に統一すると国 会で制定されることとなった。 そのために、早く確実な斬首機械として生み出されたのがこの断頭台(ギヨティーヌ)である。 一説によると、どんな太さの首でも切断出来るよう、ギロチンの歯を斜めにし三角形のような形にするよう提案したのは、機械に詳しかったルイ16世だったと言われている。
クラヴァット17世紀から19世紀に使用された、現在のネクタイの祖とされる服装の形式。スカーフ状の布を首に巻いて使用する。太陽王ルイ14世がクラヴァットを大変気に入り、宮廷ファッションとして積極的に取り入れた。
グレゴリウス暦
1582年にローマ教皇グレゴリウス13世によって制定された暦。現在の太陽暦のこと。
フランスでは制定年である1582年に導入されたが、革命暦の使用開始により一時中断。が、十進法を基礎に作られた革命歴は使いにくく、特に農村部からは激しい抵抗があった。その後1806年に革命暦は廃止される。
南フランスの小都市・パミエ出身の女優。1792年、パリに乗り込んで女性会員だけの政治結社「共和主義女性市民の会」を設立した。初めはジロンド派を激しく攻撃していたが、彼らが失脚すると次にはジャコバン派を攻撃するようになり、この過激な主張と行動ゆえに公安委員会から危険分子扱いされるようにある。 1794年に逮捕され、その後は恐怖政治に失望して女優に戻ったとされているが、消息は定かでない。
激昂派ジャック・ルー、ジャン・フランソワ・ヴァルレらを中心とした議会における極左の一派。ルイ16世処刑後のパリは物不足となり、釣り上がり続ける物価に、市民らは深刻な飢餓に陥った。その状況に対しルー、ヴァルレらは買占め人の処刑や政府による価格統制などを唱え、貧困にあえぐ市民らの共感を得た。
嫌疑者法
1793年3月には革命裁判所が設置され、同年9月には簡単な密告だけでも隣人を「反革命容疑者」として告発できるような「嫌疑者法」が導入された。また同時にサン=ジュストは、反革命容疑者の財産を革命政府が没収し、貧しい人々に分け与えることができる「バンドーズ法」を制定する。これらの法律は革命裁判所の迅速な審理とあいまって、多数の「容疑者」の財産を奪い、彼らを断頭台送りにした。恐怖政治の象徴とも呼べる法である。
また同年には亡命者に対する法も一層苛烈になり、亡命者がフランスに帰国した場合には死刑となり、その財産は没収されることが定められた。
王が承認し、発行する書状に国璽を押印、またその国璽を保管する閣僚のこと。現在のフランスでは司法大臣が国璽尚書を兼ねている。
国民公会王政が廃止され、新たなフランスに秩序をもたらすべく1792年9月に成立した革命政治の立法、行政を担った機関。ジャコバン派、平原派、ジロンド派の主に三つの会派に別れ、平原派が最大会派であった。
コルドリエ・クラブ正式には「人間と市民の権利の友人会」。1790年、コルドリエ修道院にて結成された。デムーランやダントンなどを擁したが、のちに恐怖政治を主張する極左のエベール派が台頭、分裂した。
コンシェルジュリフランス王家がパリに築いた最も古い王宮。14世紀ごろから牢獄として使われ始め、マリー・アントワネットもタンブル塔からここに移送され、ギロチン台に登るまでの日々を過ごした(現在、マリー・アントワネットが過ごした牢獄は一部復元され見学できるようになっている)。革命後は国民公会により「革命裁判所」がここに置かれ、貴族から庶民まで多数の人間がギロチン台へと送られた。1914年に牢獄としての役割は廃止され、歴史遺産として観光名所になっている。
1793年5月4日、ジロンド派と山岳派が激しく争う中、国民公会により「穀物価格の最高額を定め、
取引を規制する法律」が制定された。これは所持している穀物量についての自己申告にはじまり、またその集計、調査、家宅捜索を行うことを定め、違反した場合においては、その者への罰則などを定め、恐怖による物価統制の始まりとなった。穀物のみに限られていたその法律は9月11日には家畜飼料を、同月29日には生活必需品全ての価格を当局が管理するよ
う範囲が広がった。
この法律が適用されるとパリは瞬く間に極度の物不足に陥り、また闇市場が急速に生まれた。
タイトルは、フランス語で「なんとかなるさ、うまくいくさ」などの意味を持つ成句。もともとは舞踏用の曲であったが、1790年の全国連盟祭の時に市民が「貴族を縛り首に!」と過激な替え歌として歌ったため、民衆の間に爆発的に広まった。
サド侯爵「サディズム」の語源になった、フランス革命時代の小説家。宗教・法律・良心の制限をうけない、暴力とエロティシズムに満ちた小説を数多く残している。その多くは19世紀まで「禁書」とされ一般に読むことはできず、またサド自身も生涯の三分の一あまりを監獄で過ごした。革命前夜にはバスティーユに投獄されていたが、革命の影響で解放された。しかしナポレオン体制下で「狂人」とみなされ精神病院に監禁され、そこで生涯を終えた。
サルディニア王国1718年に締結されたロンドン条約により、1720年、サヴォイア公アメデーオ2世を始祖として建国された王国。イタリア半島の西部にある「サルディニア島」と、フランスのサヴォイアとニースを領土とした。フランス革命時にはオーストリア側で参戦したが、ほどなくフランス軍に敗戦、サヴォイアとニースを失地した。
三月の聖週間十字架にかけられたイエス・キリストが三日後に蘇ったことを記念する「復活祭」までの一週間をさす。春分の日を起点に復活祭の日が決められるため、毎年期間は異なる。イエスのエルサレム入城から受難の日までを象徴するキリスト教で最も大切な行事とされ、プロテスタントでは「受難週」と呼ばれている。
三頭派パルナーヴ、デュポール、ラメット兄弟らなど。1791年の憲法成立時においては「一院制で、議会の決定に対し国王は限定された拒否権を持つ」立憲君主制を主張した。
サン=ドマング島現在のハイチ共和国にあたる、1790年当時においてはフランスの植民地のうちではもっとも豊かだった島。入植したフランス人はコーヒー・砂糖・タバコなどのプランテーションを次々と建設し、アフリカ大陸から奴隷を輸入して働かせ、巨万の富を本国にもたらした。1790年10月、パリで革命を体験したムラート(白人と有色人種の混血)のヴァンサン・オジェが人権宣言をサン=ドマングでも適用させようと上陸、白人と有色人種の対立を引き起こし、大規模な反乱に発展した。
三部会中世~近代フランスで存在した、アンシャン・レジームすべての身分の代表が集まる議会のこと。1302年に初めて招集された。ルイ13世時代の宰相・リシュリューにより一時廃止されたが、1789年、ルイ16世が170年ぶりに全国三部会を招集。財政改革を論じ合うためのものであったが、これがフランス革命を誘引し、最後の三部会となった。
シスマ「分裂」を意味するラテン語。教会分裂のことを指す。教義を理由に教会が分裂するのではなく、教会の組織的な事情(教皇の資質、要人の地位)などに異を唱えた集団が教会を離れることを言う。
シテ島パリ発祥の地、と呼ばれるセーヌ川中洲にある小さな島。ここにはノートルダム大聖堂、サン・ミシェル教会、コンシェルジュリ、と中世の名だたる建築物が残されている。
ジャコバン・クラブ1789年、パリ・ジャコバン修道院で「憲法の友の会」の名前で設立された、左派議員の集うクラブ。元は様々な思想家たちが集う場所であったが、革命が深化するにつれて急進的な左派の集団(山岳派)となった。ロベスピエールやサン=ジュストがクラブの中心人物である。
シャルロット・コルデー
革命の指導者・マラを暗殺した元修道女。
ノルマンディー地方の没落貴族に生まれたシャルロットは、13歳のときに母を亡くし、女子修道院に入る。が、革命が起こって修道院が閉鎖され、革命で混乱する俗世に再び戻されるこことなる。
混乱する社会を目の当たりにしたシャルロットは、革命を推進するジャコバン派、特にマラのせいであると思い込み、殺害を決意する。また、彼女がいた都市・カーンが逃亡してきたジロンド派の議員らの拠点となっており、彼らとの交流があったことも、彼女の決意に大きく影響を与えたと言われている。
マラ殺害後、現行犯で逮捕された彼女は4日後に処刑されている。愛らしく儚げなたたずまいから、後のロマン派詩人ラマルティーヌに「暗殺の天使」と名付けられた。また国会議員の資格を持っていたアダン・リュクスという男は断頭台へ向かう彼女に求婚し、あまつさえ彼女と同じギロチン台で処刑されることを熱望し、彼女を讃えた罪で望み通り死刑判決を受けている。
1689年ー1755年。ボルドー生まれの啓蒙政治思想家、および哲学者。自らも男爵の爵位を持ちながら、フランス絶対王政を批判。著作である『法の精神』で「立法」「行政」「司法」の三権分立理論を打ち立て、中央集権制からは真の政治的自由は生まれないと説いた。
ジャン・カルヴァン16世紀に活躍した、キリスト教宗教改革の中心人物。ロベスピエールと同じフランス・ピカルディの出身。人は信仰のみによって救われ、そのため日々の生活も規則正しく、勤勉に労働せねばならないと説いた。礼拝の形式や教会組織のありかたでカトリック派と激しく対立、スイスに亡命し、自らの思想の集大成である『キリスト教綱要』を著す。のちのプロテスタント思想の発展に大きな役割を果たすこととなった。
ジャン・ジャック・ルソー(1772-1778)主にフランスで活躍した思想家・小説家。主な著作に『エミール』『告白』『社会契約論』など。近代の憲法の基礎ともなる考え方「社会契約」という言葉を始めに使ったのは彼である。『社会契約論』の「社会および国家は自由な個人間の契約によって成立する」という思想はフランス革命に影響を与えた。
重農主義18世紀後半、フランスのケネーらによって説かれた「生産を行う農業こそが富の源泉である」という経済学の考え方。商業や工業は原材料がなければ何も生み出すことはできないため生産性がないとし、14世紀にコルベールらが説いた「重商主義」とは対立する考え方である。農産物の自由交易化や土地に対する課税などで国庫の充実を図ろうとし、財務長官テュルゴーが積極的に政策へ取り入れた(後に彼は失脚、ネッケルが後任として任命される)。この思想はのちにイギリスのアダム・スミスに影響を与えた。
ジロンド派1791年、立法議会が成立した際に主導権を握った政治派閥。元々はジャコバン・クラブに所属してい た議員たちの集まりで、ジロンド県出身の者が多かったために、後世の歴史家によってそう名付けられた。主なメンバーはブリソ、ヴェルニョー、ペティオンら で、後に「ジロンド派の女王」と呼ばれるロラン夫人のサロンに集った。1792年政権を握りオーストリアと開戦するが、ラ・ファイエットをはじめとするフランス軍は各地で連敗。敗戦の責任を取るためにフイヤン派に政権を譲り渡した。
神聖ローマ帝国962年~1806年の間、ドイツを中心に西ヨーロッパに広く存在した国の名。数多くの小公国、地方や辺境の伯爵領など数多くの国家から成る連合国だった。その皇帝は世襲制でなく、「選定侯」と呼ばれる有力領主によって選ばれ、他の国家に比べて皇帝の権力は弱いものであった。が、1404年にハプスブルク家が皇位を手にすると、その後強固な世襲制が敷かれ、1806年にフランスのナポレオンが攻め入るまではハプスブルク家の時代が続いた。
セーヴル焼フランス・ロココ文化から生まれた優雅、洗練を極めた陶磁器。 1738年、当時の大蔵大臣フルビーが陶工デュボア兄弟を招いてパリ東部郊外ヴァンセンヌに窯を開いたことが始まり。ルイ15世の治世においてはポンパドゥール侯爵夫人がパリとヴェルサイユ宮殿の間にあるセーヴルに窯を移し、一流の陶磁器を作るよう命じた。「フランス宮廷の威信をかけて、他国の宮廷に負けない美しい陶磁器を作りたい」——国王以上に芸術に理解を示したポンパドゥール侯爵夫人の情熱から、「王者の青(ブ リュー・ド・ロア)」や「ポンパドゥール・ローズ」などの美しい彩色をもった作品が生まれた。
草月法
別名「恐怖政治法」。革命裁判所の司法手続きを改める法律で、これにより裁判官の「愛国心」が罪状判断の基準とされ、また全ての市民が疑わしきものを告発することができるなど、恐怖政治の加速を促すものであった。また、全ての罪に対する刑は「死刑」のみであった。
この法律が適用されてからギロチンの犠牲者はいっそう増大し、その中には多くの無実の者が含まれていた。その恐怖が他の議員たちを「打倒ロベスピエール」へと駆り立て、テルミドールの反動へとつながってゆく。
国王ルイ16世を処刑したフランス。諸外国はそれを「自国の君主制に対する挑戦」とみなした。イギリスの宰相ピットは1973年1月24日、フランスに対し国交断絶を通達。またブルボン朝の分流を王家に戴くスペイン、ナポリはフランスを明らかな敵とみなす。そこに教会改革に憤怒するローマ、すでに戦争を始めているオーストリア、プロイセン、またネーデルラントやサルディーニャなどの各国を加えると大包囲網が完成、フランスはほぼヨーロッパ全土を敵に廻した形となった。
タリアン
本名ジャン=ランベール・タリアン。初期からの熱心な革命支持者でジャコバン派。1793年に反革命派の粛清のためにボルドーへ派遣され、そこで裕福な銀行家の娘で元公爵夫人のテレーズ・カバリュスと出会い、恋に落ちる。
彼女のために反革命派の粛清に手心を加えたことがパリのロベスピエールに伝わると、ロベスピエールはタリアンをパリに召還。その後を追ってきたテレーズはそのまま逮捕され、監獄に収監される。
彼女は出獄するためにタリアンヘ大量の書状をしたため、その文面が反ロベスピエールに揺れていたタリアンの心を決意させる。タリアンはジャコバン派の議員で貴族階級出身のバラスとともにテルミドールのクーデターを起こし、ロベスピエールを失脚させ、断頭台へと送った。
タリアンは出獄したテレーズと結婚したが、一年ほどで離婚。その後も政治の場にとどまるが目立った功績はあげられなかった。
本名ジャン=ランベール・タリアン。初期からの熱心な革命支持者でジャコバン派。1793年に反革命派の粛清のためにボルドーへ派遣され、そこで裕福な銀行家の娘で元公爵夫人のテレーズ・カバリュスと出会い、恋に落ちる。
タルペイアの岩
古代ローマ・カピトリヌスの丘にある断崖で、かつてはローマを守る砦として使われていたが、後には国を裏切る重罪犯を突き落として殺す処刑場となった場所。
「タルペイア」はこのカピトリヌスの丘の守備隊長であったタルペイウスの娘の名。北東のサビニ族がローマに攻めてきたときに、彼女は(「サビニ人が腕につけている装飾品を欲しがった」あるいは「サビニの敵将タティウスに一目惚れした」「ローマを勝たせるためにサビニ人が身につけていた盾を要求した」などさまざまな伝説があるが真相は不明)この城門を開けてしまう。サビニ人が砦を制圧した後、彼らは持っていた盾をタルペイアに投げつけ圧死させてしまったという。
1664年、ルイ14世の時代に完成した王宮。完成するまで100年の年月を要した。1683年にヴェルサイユ宮殿が完成するまでは王宮として使用された。ルイ16世が革命政府により逮捕されたのちは公安委員会の拠点などに使用されたが、のち、ナポレオンが王宮とした。1871年にパリ=コミューンで炎上し、1883年に解体された。現在は庭園のみが残っている。
テレサ・カバリュス
スペインの銀行家カバリュスの娘で、美貌の女性。宮廷の華やかな生活に憧れ、16歳で老貴族ド・フォントネ公爵のもとに嫁ぎ、社交界入りを果たす。
ラファイエットやラメット兄弟など当時の貴族を親交を深め、革命に興味を持つ。革命の激化を恐れ亡命を決めた夫とは離別、自身はボルドーへと移り、そこで出会ったタリアンの愛人となる。
タリアンはテレサのいうがままに、彼女の友人である反革命容疑者たちを処刑のリストから外すなど不正な行いを重ね、パリのロベスピエールの不興を買ってパリへと呼び戻される。
タリアンを追ったテレサはパリで逮捕、ラ・フォルス監獄に収監される。そこで彼女がタリアンに向けて書いた出所の催促をする手紙がタリアンの焦燥をあおり、かねてから誘われていた「テルミドールのクーデター」への参加につながった。
クーデターは成功。テレサは釈放され、「テルミドールの聖母」と呼ばれるようになる。またのちにタリアン夫人としてサロンを開き、ファッションリーダーとなってギリシャ・ローマ風の衣裳を流行させた。
エベールが発行する新聞。パリに暮らすサン・キュロットであるデュシーヌ親爺が、仲間と共に粗野な言葉遣いで世相を切って捨てるという、キャラクターを使った物語仕立ての、今までになかった形式の発行物で庶民の絶大な支持を得た。この庶民の人気がエベールを革命の中心へと押し出してゆく。
天然痘疱瘡とも呼ばれる、強い感染力をもつ伝染病。高熱と頭痛に始まり、発症してから2~3日後に発疹が表れる。致命率は比較的高いが、治癒した後でも疱瘡の跡が残る「悪魔の病」。1980年、WHOによる根絶宣言がなされ、現在では患者の報告はされていない。
トマス・ペインイギリス・ノーフォーク州の職人の家庭生まれ。職を点々としていたが、1774年、独立の機運高まるアメリカに渡り雑誌記者として活躍。1776年、フィラデルフィアにて「アメリカがイギリスの支配から独立するのは当然のことである」といった内容を平易な言葉で説いた政治パンフレット『コモン・センス』を出版。市井の人々に独立を強烈に意識させるきっかけとなった。またフランス革命を支持し、第一共和政の国民公会にも参加。ジロンド派の憲法草案の制作にも携わったが、ジロンド派の没落と共に、その憲法は成立することがなかった。
フランス・ロレーヌ地方の都市。1790年8月、ここで貴族出身の士官と平民の兵士の間にいさかいが起き、そこに市民軍が介入して大規模な反乱に発展した。ラ・ファイエットはこの反乱を鎮圧するためにブイエ将軍に進軍を要請。結果として1000人以上の死者が出た。このためラ・ファイエットはマラなどから激しく批判され、人望を失った。
ヨーロッパ最古の大学のひとつで、起源は12世紀にさかのぼる。1275年にソルボンによる神学部学生のための学生寮が創設され、そのため「ラ・ソルボンヌ」とも呼ばれる。その後ローマ教皇の許可を得て、神学の殿堂と言われるべき存在となった。革命時に一時廃止され、1808年ナポレオンの「帝国大学令」により再開した。
パンテオンギリシア語で「万神殿」を表す言葉。本書に出てくるパンテオンはパリ五区、サント・ジュヌヴィエーヴにあり、元は病いを患ったルイ15世が、その健康の回復をパリの守護聖人「聖ジュヌヴィエーヴ」に感謝し建築されたもの。現在はフランスの為に尽くした功労者たちが埋葬されている。またフーコーの振り子の実験場所ともなったことで有名。
百科全書派1752年~1780年にかけて、フランスで断続的に編集された『百科全書、あるいは科学・芸術・技術の理論的辞典』に執筆、編集協力した思想家たちを指す。おもにディドロとダランベールにより共同編集がなされた『百科全書』は、著名な知識人だけでなくあらゆる思想の持ち主の寄稿、共同編集を実現させ、フランス思想界の近代化を大きく促した。
ピルニッツ宣言1791年8月、王妃マリー・アントワネットの兄である神聖ローマ皇帝レオポルト2世と、プロイセン国王ヴィルヘルム2世がピルニッツ城(現在のドイツ・ドレスデン市)内で会見した際、妹・マリー・アントワネットの身を案じるレオポルト2世が、ルイ16世の弟アルトワ伯の仲介により「必要に応じて、革命下のフランスに各国と共同で武力行使する用意がある」と世に発した。
ファブリキウスの茅屋、クラックスの宮殿ロベスピエールが議会演説の際に用いた例え。ファブリキウスは非常に貧乏だったが公明正大、清廉で知られたローマの執政官。その徳の高い人物評は後世のルソーの著作にまで記されるほどであった。クラックスはカエサルの第一次三頭政治に参加した、当時のローマで一番の資産家。
フイヤン・クラブ正式には「憲法友の会」。ラ・ファイエットやデュポール、パルナーヴ、ラメットらの三頭派、シェイエスらが1791年に結成。ブルジョワ層を多く擁する彼らは「ヴァレンヌ事件」で王の責任を不問に処し、富裕層に有利な憲法を成立させた。
風月法サン=ジュストが国民公会に提出した法案。反革命容疑者の財産を没収し、貧民に分け与えて富の平等をはかろうとした法案である。これは国民公会において満場一致で可決されたものの、実行はなされなかった。当時の議員のほとんどが大土地の所有者であり、ブルジョアの利益を代表していたからである。
プティ・トリアノン宮1768年、ルイ15世が愛妾・ポンパドゥール夫人のために立てた離宮。が、完成時すでに夫人は亡く、ルイ16世によって王妃マリー・アントワネットに与えられた。彼女はここをイギリス風の庭園に改造し、農村風の建物や牧場を作り、お気に入りの貴族だけを招き入れて「農婦ごっこ」にふけった。一説では、王妃はこの離宮の改造に20億円ほどの税金を浪費したと言われている。
フランス衛兵隊1563年、シャルル9世によって創設された、王制を守るための軍隊。パリだけでなくフランス全地域から兵員を募集。また貴族だけからなる近衛兵と違い、平民出身の兵隊も多かったため、いち早く王制側から革命勢力に加担、参戦したと言われている。
フランス革命暦(共和暦)
キリスト教を否定する革命政府が導入した新しい暦。王制が廃止された1792年9月22日(この日付自体はグレゴリオ暦)を元日とし、365日を12の月に分け、それぞれに詩人・デグランティーヌが名を付けた。名は以下の通り。(※日付はおおよそのもの)
9/22〜 葡萄月(ヴァンデミエール)
10/22〜 霧月(ブリュメール)
11/22〜 霜月(フリメール)
12/22〜 雪月(ニヴォーズ)
1/22〜 雨月(プリュヴィオーズ)
2/22〜 風月(ヴァントーズ)
3/22〜 芽月(ジェルミナール)
4/22〜 花月(フロレアール)
5/22〜 草月(プレリアール)
6/22〜 収穫月(メッシドール)
7/22〜 熱月(テルミドール)
8/22〜 実月(フリュクチドール)
1791年に発行された、カミーユ・デムーランによる新聞。「ブラバン」は首都ブリュッセルを含んだベルギーの州名だが、1995年にブラバンフラマン州とブラバンワロン州に分離されている。
フランス式ボクシング
ブルボン朝時代に紳士の護身術として発達した格闘技。サバット(靴)を履いて相手を蹴る蹴り技が主体。ムエタイやキックボクシングとの類似が指摘されるが、硬い靴を履いて行うルールであるために、脛でキックを受けないなど、異なるところが多い。
プロレス技の「ソバット」はここが語源である。
熱帯、亜熱帯の土地を大規模な農地として経営し、単一の作物を生産・栽培する農園のこと。輸送システムや作物の加工などを一括で行えるため安定した経営が可能だが、植民地時代には先住民の土地を奪った上で彼らに奴隷労働を強いた。また現代においては環境破壊の問題などを引き起こしている。
ブルボン王朝1589年、フランス・ブルボン家のアンリ4世が王として即位したのが始まり。フランス革命でルイ16世が処刑されるまで約200年ほど続いた。フランス文化の礎はこの時代に築かれたが、華やかな貴族文化と度重なる戦争で国庫は疲弊。ルイ16世は、今まで税を支払わなかった特権階級に税を課すことで財政破綻を乗り切ろうとしたが、全国三部会は紛糾、のちのフランス革命につながる。
平原(プレーヌ)派国民公会の議席の、比較的下のほうに陣取っていたことからそのように呼ばれた一派。日和見主義であったと評されることも多いが、議会内では最大数の議員を有する会派でもあったため、常々ジロンド派とジャコバン派の対立を左右する動きを見せた。
プロイセン1701年ー1918年まで続いた、現在のドイツ北部、ポーランドの一部を含む王国。13世紀にヨーロッパの有力騎士団であった「ドイツ騎士団」の領土が国家に発展したことからその歴史が始まる。1701年に神聖ローマ帝国のブランデンブルク選定侯フリードリヒ3世が帝国領土の外にあったプロイセンを王国とし、初代プロイセン王となった。
ベンジャミン・フランクリン(1706-1790)アメリカ合衆国の学者、政治家。現在の100ドル札に彼の肖像画が使われている。独立戦争中は欧州諸国との外交交渉を行い、フランスの参戦を促した。アメリカ独立宣言の起草委員でもある。また、雷が電気であることを発見したのは彼である。
ホラティウス兄弟の誓い
国民公会の議員でもある画家、ジャック・ルイ・ダヴィット作の絵画作品。1784年に王から依頼を受け描かれたもの。
紀元前7世紀に争っていた二つの都市・ローマとアルバでは、闘いに終止符を打つためにそれぞれの都市から闘士を選出、彼らの決闘をもって勝敗を決することになった。ローマからはホラティウス三兄弟が、アルバからはクリアトゥス兄弟が――。
姻族関係にあるふたつの家族が都市を代表して死闘を繰り広げる情景を描いたこの絵は愛国心や忠誠心を表現したものとして、国王、貴族や聖職者らから大変な称賛を受けた。
が、1789年にダヴィッドは『ブルートゥス邸に息子たちの遺骸を運ぶ警士たち』で暴君カエサルを暗殺したブルートゥスを英雄として描いている。生粋の画家はこの絵をきっかけに、深く革命へと身を投じることになる。
銃口から火薬を流し込む「先込め式」の歩兵用の小銃のこと。当時のフランス軍隊の主流の武器であった。
マルク銀貨法一定の納税額(1マルク銀貨)を払うことができる市民を「能動市民」、払うことができない市民を「受動市民」と分け、受動市民には選挙権を与えないとした選挙法の事。国民衛兵隊に入隊できるのも「能動市民」だけとし、富裕層のみが政治に参加できるしくみを作り上げるものとなっていた。
モリエール(1622-1673)17世紀に活躍したフランスの喜劇作家。代表作に『ドン・ジュアン』『町人貴族』など。
モンゴルフィエ兄弟
世界で始めて熱気球を発明し、有人飛行を行った兄ジョセフ=ミシェル・モンゴルフィエと弟ジャック=エティエンヌ・モンゴルフィエの二人。
発明のきっかけは暖炉の炎で乾かしていた洗濯物。布地が熱気で浮き上がり、熱気を包み込むような形になった状態を兄ジョゼフが発見、そこから熱気球の基本の仕組みを思いついた。
兄弟は試作を重ね、1783年にはルイ16世とマリー・アントワネットの御前で公開実験を行う。その際には羊、あひる、鶏を乗せ、高度が生物にどのような影響を及ぼすのかが観察された。気球は500
mの高さまで上り、3.5kmの飛行を経て無事に着陸した。
モンゴルフィエ兄弟が始めて公開飛行を行った6月5日は、今でも「熱気球の日」とされている。
10世紀半ばに豪族ロベール家の長男として生まれ、父・ユーグ大公が死去したあとはその跡を次ぎ、家長となった。幼くして家督を任されたために部下の離反などを止められず、領土の多くを失いもした。 987年、それまで西フランク王国(現在のフランスの原型となる国)を統治していたカロリング朝のルイ5世が急死。そのときにランス大司教の後押しで西フランク王国の王として即位する。ここをフランス王国の始まりとする説が一般的である。「カペー」はフランス語でケープの意。
現在のフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」の原題。1792年4月、アルザスの都市ストラスブールの市長ディートリッシュが、軍を鼓舞するために当時の工兵将校・ルージェ・ドゥ・リールに作曲を依頼し、一夜のうちに完成した曲。この歌は爆発的に流行し、軍では歌えないものはいないくらいになった。パリにこの曲を持ち込んだのがマルセイユの連盟兵たちであり、そのために「ラ・マルセイエーズ(マルセイユ野郎どもの歌)」と呼ばれるようになった。「残忍な敵兵どもが君の息子や妻の喉を裂きにやってくる」などの歌詞が他国を敵視するものであり、現代の国情には合わないのでは、との議論が現代のフランスでは起き、たびたび歌詞改正の動きが起こるが、未だ往時のままの歌詞で歌われている。
ラヴォワジエ
「近代化学の祖」と呼ばれる偉大な化学者。化学反応をした後も物質の質量は変化しないという「質量保存の法則」を発見した。
科学が錬金術との境界をあいまいにしていた当時において、1789年「科学言論」を出版、現代の元素に通ずる物質のリストを発表。化学の確立に大きな功績を残す。
が、科学者である傍ら徴税請負人としても働いていたことが災いし、1793年革命政府により逮捕。1794年ギロチンにより処刑。マリー・アントワネットの数学教師を務めていた天文学者のジョゼフ=ルイ・ラグランジュは、「彼(ラヴォワジエ)の頭を切り落とすのは一瞬だが、彼と同じ頭脳を持つものが現れるには100年かかるだろう」と彼の才能を惜しんだ。
ルイ13世の宰相を務めた、カトリック教会の聖職者。現パレ・ロワイヤルの住人であった。 ブルボン王朝の繁栄に尽力し、近代フランスの基礎を築いた有能な政治家であった。三部会を廃止するなど中央集権と王権の強化を進めるなどし、絶対王政の基礎をゆるぎないものにした。
リュー欧米で使われる距離の単位で、古代ローマに語源を持つ。革命当時のフランスでの1リューは4km前後であった。
竜騎兵馬に騎乗したまま戦う兵士のこと。フランス革命勃発時、国内には18個連隊の竜騎兵がおり、マスケット銃と剣の装備で武装していた。
ルイ・ル・グラン学院(ルイ大王学院)1563年、カルチエ・ラタンの中心に建てられた教育機関。ロベスピエール、デムーランをはじめ、創立以来多くのエリートを輩出している。主な卒業生にロマン・ロラン、ジャン=ポール・サルトル、マルキ・ド・サド、ドラクロワ、ジャック・シラクなど。