

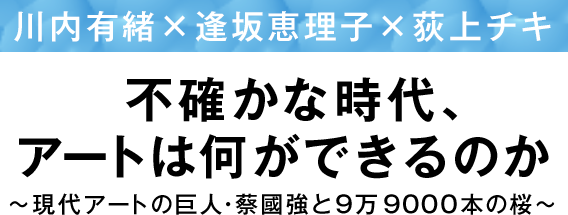
川内 蔡さんが第7回ヒロシマ賞を受け、2008年に広島市現代美術館で企画した「黒い花火」という作品があります。原爆ドーム周辺の上空に1000発の黒い花火を打ち上げるという作品なんですが、この企画の4日前に、東京の芸術家集団チンポム(Chim↑Pom)が自分たちで飛行機をチャーターして、「ピカッ」という白文字を空に描くという企画を行ったそうです。
チンポムは、私はとても好きなアーティストで、空に原爆をイメージさせるようなものを描くという意味では同じだったのですが、市民の反応は真逆で、「黒い花火」は受け入れられ、「ピカッ」は大きな物議を醸しました。現代美術で、このように受け入れられるものと、受け入れられないものの違いは何だったのか。逢坂さんはどうお考えになりますか。
逢坂 私は「黒い花火」のほうは実際見ているんです。私が想像するに、カタカナの「ピカッ」という言葉が広島の人たちに与える負のイメージは非常に大きい。原爆の後遺症に長い間悩まされている人たちの思いを考えると、「ピカッ」を空に描くこと自体が、原爆そのものを象徴してしまうと思うんです。だから、チンポムが事前にもっと調査していれば、違う表現の仕方があったんじゃないかと。
一方「黒い花火」というのは、のちに広島が立ち上がったことに対する希望と、亡くなった人々の鎮魂を意味している。当然事前にいろんな許可をもらう必要がありますから、おそらく蔡さんは、関係者、市民、行政の人たちに作品の意図を伝えていると思うんです。そこの差だったのかなと思いますね。
荻上 合意形成のプロセスとしては全然違いますよね。チンポムのメンバーは、これが物議を醸して以降、広島の方々とコミュニケーションを深めていった。そういう意味では、その後の責任をとろうとされたわけです。「ピカッ」というのは、それこそ差別的に使われた「ピカドン」だったり、カタカナの「ヒロシマ」のイメージと重なる。震災後の「フクシマ」と同じで、周りから名づけられたものであると。チンポムは、そういった現実を表現したかったようですが、オーディエンスが誰かという認識がやや不透明だった。2作品は、合意形成と見る側をどこに置くのかというところが随分違ったという印象ですね。
アートという同じ文脈のなかで、同じような題材を取り上げながら、これだけ見る者に与える影響が違う。それは何に由来するのかというのは、アートの外側においては、コミュニティとの合意と、見る者に対する歴史への平準化。そんななかで蔡さんは、今を生きる人たちが、何をその地域に残していくのかというのを意図的にやっているんだと語っている。
川内 アートは面白いですよね。どの角度から、どう見るかで違うし、それがどういう気持ちを喚起させるのかということを考えていくと、無限の可能性がある。
逢坂 今、グローバリズムが浸透して、どの大都市でも同じ店舗があったり、似たような街並みだったりと、物質的な文化がどんどん画一化されている一方で、対立は絶えない。情報の洪水のなかで確実な道筋を選ぶことが難しいこの不確かな時代に、私たち一人一人が自分の足で立たなければいけない部分がどんどん大きくなっていると思います。そのとき、全ての人が一緒に理解し合うというのはあり得ないわけです。
でも、いい作品というのは、見る人に、一つの答えではなく、様々な解釈を与えてくれる。そこから違う解釈や価値観を持っている人の存在を知ることができる。そして、自分とは違う人との共生を考えたとき、アーティストが持つ色々な視点や現代美術が示してくれる様々なメッセージが、自分の頭を柔らかくするための一つのきっかけになると思います。
荻上 アートというと、そこには何か巨人がいて、見る側とは線が引かれていて、何か特別な創造力がある、といったステレオタイプで描かれると思うんですが、この『空をゆく巨人』は違って、よき美術ガイドであり、現代社会ガイドでもある。二人の巨人の物語だけではなく、背景の様々な小さな出会いの蓄積により、蔡國強が形成してはまた生まれ変わっていくというさまを、すごく丁寧に描いている。ドキュメンタリーとしてすごく力がある作品だと思いました。
逢坂 蔡さんと志賀さんがつくり出す創造的な世界が、説得力をもってまとめられていて、私も本当に楽しく読ませてもらいました。
川内 ありがとうございます。現代美術がわからない方にも、読んでいただけたらうれしいですね。
荻上 この本を読んだ上で、実際の蔡さんのアートに触れるのもよし、さらに、志賀さんたちのプロジェクトを確認して、「不確かさ」を許容できるようなアート表現というものを実感していただければと思いますね。