

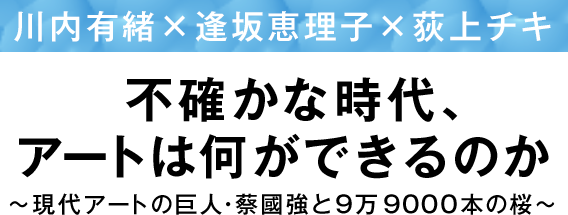
荻上 僕は被災地に行って、被災者の方やNPOなどの支援団体への取材をよくしているのですが、その場所をどう復興していくのかというとき、「いわき万本桜プロジェクト」のように、色々なモニュメントやアート、プロジェクトを具体的な復興のシンボルにしていくという活動があちこちで行われています。
桜つながりでいえば、陸前高田市(岩手県)の「桜ライン311」。これは1万7000本の桜を、津波の最大到達地点をつないだライン上に植えていくことで、離れ離れになってしまった人たちを再び集められる場所にしたいという思いから立ち上げられました。桜を植えるのは他県から来たボランティアの人たちで、1本1本の木のオーナーになってもらい、その場所はあなたの土地でもあるというように体感してもらう。加えて、桜が咲くのが3~4月と震災があった時期に近いので、花見など楽しい思い出をつくってもらうと同時に、震災の記憶をよみがえらせ、次の世代に語り継いでもらう、という試みなんです。これは防災学では、結果防災といわれる活動になります。花見という行事で毎年その場所に通うことで、災害の記憶や知識が自然とインストールされていくわけです。
「いわき万本桜プロジェクト」と「桜ライン311」は、同じ桜という観点でも全く異なるアプローチです。お二人は、この二つの活動の区別をどうお考えでしょうか。
逢坂 志賀さんは企業人ですが、まるでアーティストと同じように、いかに拘束されず自分を自由に解き放っていくかということにすごく意識的な方だと私は思っています。放射能の影響がなくなるまで何万年とかかる。そこへの思いや怒り、そして未来の子どもたちへの思いから、志賀さんたちは、この9万9000という途方もない数字を出して、原発中心の今の社会にメッセージを発信している。大切なのは、活動家として運動するのではなくて、自由であるということ。
桜を植えるプロジェクトのなかで、桜だけでなく、放射能に耐性があるという菜の花も植えたり、さらには回廊美術館があったり、ブランコやステージがあったり、皆が集える場もある。自由でありたいという意識が見えるところが特徴的だと感じます。
川内 この回廊美術館という構想は当初はなく、桜を植えている皆の姿を見た蔡さんが、「この辺に美術館をつくれないですかね」といって始まったんです。山の管理は肉体労働が中心で、ただ桜を植えるだけだったら、やっぱりつらいことが多い。でも美術館ができたことで、来た人も楽しめるし、志賀さんたちも作品をどんどんつくっていくという楽しみができた。「蔡さんは、俺らに楽しみ方を教えてくれているんだな」と志賀さんはおっしゃっていたんですよね。
また、このプロジェクトは、公的資金を入れたいという話があってもお断りをしている。それは今、逢坂さんがいわれた、自由でいたいというのともう一つ、これが決して復興プロジェクトではないということ。これはすごく重要なことです。自由に楽しみながら自分たちの怒りを鎮めておくプロジェクトであるということをとても大事にしている。私はそこにすごく共感しています。
荻上 先ほど「宇宙と対話する」という話がありましたが、蔡さんの作品には、宇宙からも見られるような壮大なものがありますよね。桜の植樹も歴史を次世代に刻むということで、地球に刻むといった地勢的な思いがすごく感じられる。地球を一つのキャンバスにしているような印象を持ちました。
