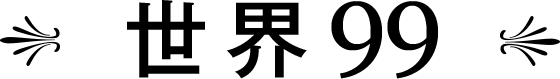トークイベント「村田沙耶香の〈世界〉」【後編】
こちらの記事は後編です。
登壇者:村田沙耶香(『世界99』著者/作家)、辛島デイヴィッド(作家/翻訳家)、由尾瞳(早稲田大学文学学術院教授)
構成/長瀬海
海外で書かれた『世界99』

辛島 『世界99』の連載がスタートした2020年10月は、ちょうど『地球星人』の翻訳が各国で刊行されはじめていた頃でした。まだコロナ下で移動の制限はあったものの、海外のフェスティバルに加えてレジデンシーからも多くのお誘いがあり、国内外を行き来しながら執筆活動をされていたかと思います。ニューヨークのArt Omiにも滞在されていましたね。これは作家が創作のために海外に滞在するプログラム、ライター・イン・レジデンスの一つだと思いますが。
村田 各国の小説家がアイオワに3ヶ月ほど滞在するライター・イン・レジデンスは中上健次も参加したことで有名で、とても歴史がありますよね。藤野可織さんや柴崎友香さんなど私の友達もたくさん参加していて、みんないい経験をして帰ってくるので私はいいなあと憧れていたんです。そんなとき、Art Omiの存在を知りました。履歴書を書いて送ったところ、コロナ下で応募が少なかったらしく、1ヶ月滞在することができました。
辛島 そこでも『世界99』の連載を書いていたんですか?
村田 はい。前半部分を書いていました。
辛島 昨年はチューリッヒのレジデンスにも参加されていましたね。
村田 チューリッヒには半年間滞在させていただきました。Art Omiのレジデンスでは15人ほどの作家がコテージで生活し、昼はそれぞれ自由に創作し、夜は晩ごはんを一緒に食べて文学について語り合いましょう、という決まりがありました。週末はゲストを招いて、暖炉の前で文学について語り合う時間が設けられていました。でも、チューリッヒは一人で滞在するタイプのレジデンスだったので、アパートの一室で缶詰になりながら孤独に書いていました。 滞在中、チューリッヒのレジデンスで創作する作家をサポートしているパブロさんに「サヤカはどうしてそんなにたくさんデッドラインがあるんだい?」と聞かれたことがあります。連載があるからと頑張って説明したのですが、私の拙い英語力では伝わらなくて、パブロさんは不思議そうな顔をしていました。「連載」という概念はパブロさんの辞書にはなかったようです。結局、パブロさんのなかではサヤカは連作短編を書いているのだろうということで落ち着いていたみたいでした。
由尾 確かに「連載」は日本独特の出版形態ですね。19世紀イギリスでは連載小説が一般的で、例えばチャールズ・ディケンズは有名な例ですが、その後、連載という形態はあまり見られなくなりました。英語圏では、今では長編小説でもすべて書き終えてから出版する場合がほとんどです。毎月少しずつ発表するという日本式の連載は珍しいものだと思います。
村田 そうだったんですね。そうとは知らず、連載という単語を辞書で調べて見せたりしたのですが、みなさんどういうことかわからないみたいで。日本には文芸誌が毎月出ていることから説明しなくてはなりませんでした。「文芸誌」がそもそも文化として特殊なようで、結局私の英語力では全部お伝えすることはできませんでした。
村田沙耶香にとって「世界」とは何か
由尾 連載の執筆過程についての質問をいただいています。「初めての連載ですが青写真通り進みましたか? それとも連載することにより即興のように話が運動し出したのでしょうか?」と。また、別の方からは「連載中に現実世界で起こった出来事や触れた作品(文学だけでなくほかのものでも)で、小説に影響を与えたものはありますか?」という質問も寄せられています。
村田 私は一挙掲載のかたちで書くときは、最後まで一度仕上げてから、全体の構造をかちかちといじるのが好きなんです。たとえばこの友達の設定を変えると、必然的にこちらのシーンがこうなる。こちらのシーンがこうなると、否応なしにこちらのシーンで訪れる場所がここになる、というような感じです。なんとなく、秘密箱やからくり箪笥のようなイメージなんです。ここをこうして、こっちをこうすると、最後の箱の蓋が開いて、ある種の必然のようなかたちで小説が完成する。連載では最後の箱が開くところまでできないうちに掲載が始まったので、本になるまでは構造の最初に戻ることはできないんですよね。そのせいか慣れないうちは書くのが難しかったです。 しかもほぼ仕上がったものを一度書き直す作業をしてしまったら、自分が背負っている無意識の大きな袋から、記憶と混ざって新しく構築されたシーンが溢れ出した感覚がありました。人間の私は小説のためだけに世界を録画する肉体でできたカメラと感じているのですが、空子と私が録画している映像は異なるのに、どんどん光景が膨らんでいきました。とにかく、一回吐き出して本にするときに直そう、と思い、鮮明に見えてしまった光景をどんどん書き留めました。どうせだから一回ぜんぶ出してしまおうと思い、書けるものは書くことにしたんです。 でもそうやって書いていたら全然終わらず、結果的にとても長くなってしまって。私はプロットも作らないので、どんどん膨れ上がり、絶望的な気持ちになりました。毎年、朝吹真理子さんと編集者さんで忘年会をしているのですが、朝吹さんが「奇書だから大丈夫」と言ってくださったことを心の支えに書いていました。

由尾 しかしそのおかげでこれほどの大作が誕生したわけですね。この小説の主人公である空子は、まわりに合わせるようにしてその時々の状況に適した「キャラクター」を作っていく人物です。どこか『コンビニ人間』の恵子と似たところがあるのですが、不器用な恵子が社会に適応できない異物として扱われるのに対し、器用な空子は空気を読むことで完全に順応した「典型的」な存在になっていく。空子が十歳から二十歳になるまでを描いた第一章には、一人の女の子が生き延びるために自分の「キャラ」を作り、変容していく姿が描かれていて、読みながら本当に辛くなるようなシーンもありました。
大人になった空子は世界1、世界2、世界3……とそれぞれのコミュニティを器用に行き来するようになります。それぞれの「世界」には独自の常識やルールがあり、お互い接点を持ちません。そのなかでは歴史に対する解釈も異なり、信じるものも違う。まさに現代社会を寓話化しているかのような印象を受けたのですが、村田さんにとってタイトルにもある「世界」という概念はどのようなものなのかをお話しいただけますか?
村田 本作を書きはじめる少し前に「孵化」という短編を書きました。コミュニティによってキャラや口調を変える主人公が、結婚式という場で様々な知り合いが一堂に集まることになり、どのキャラで行くべきか悩むという小説です。私自身もコミュニティによって違う村田を使い分けていることにあるとき気づきました。あの統一できない感覚をまずは「孵化」に書いてみたのですが、やっぱり長編に書きたいと思うようになりました。
『世界99』というタイトルにしたのは、キャラクターだけじゃなくて世界も分裂している状況に関心があったからです。私が連載をはじめた後、2021年にカズオ・イシグロさんがインタビューで「地域を超える『横の旅行』ではなく、同じ通りに住んでいる人がどういう人かをもっと深く知る『縦の旅行』が私たちには必要なのではないか」とおっしゃっていました。そのインタビューを読んで思い出したのは、数年前にアイオワ大学にお邪魔したときのことでした。夕食のとき、先生方が政治の話をなさっていました。そのときにある先生に、このテーブルにはリベラルな考えを持った人たちが集まっているから一見そうは見えないかもしれないけど、この街では私たちはマイノリティなんですよ、ということを言われました。
でもそれはアイオワだけの問題ではないと感じました。確かに、私はどこへ行っても、自分と似たような考えを持つ人たちとお会いして話している気がします。たまに地元の友達と会うと、ふだんは接しないような考え方に驚くことがあります。同じ世代のなかでも別の世界に生きている人たちがいて、世界は分裂している。そのことをしっかりと書きたいと思い、タイトルを『世界99』に決めて連載をはじめました。
歴史のない土地
辛島 『世界99』では過去を持たない「クリーン・タウン」が舞台となりますよね。同じ価値観のクリーンな人が集まるという街の発想はどこから出てきたのでしょう?
村田 私は千葉のニュータウンで育ったのですけど、今考えるととても怖い街だったんです。森だった場所をすべて伐採して、何もない土地にし、みんながそこに新しく家を建てて暮らしていました。引っ越す前に父親に車で連れて行かれ、ここにどんどん家が建つんだよと言われたときの光景は脳に鮮明に焼きついています。似たような家が並んでいて、なんだか昆虫の繭を見せられているような気持ちがしました。
そこに移り住む前に暮らしていた別の街には歴史がありました。幼稚園に入る前のことなので朧げですが、街全体から過去の存在を感じていました。でも、ニュータウンに来た途端にそれがなくなったんです。近所に暮らす人たちも、似たような年齢の同じような経済状況の大人たちばかりで、子どもたちはまるでカプセルのなかで育てられているみたいでした。木を一つ残らず刈り取り、まっさらな上に置かれた繭のようなカプセル。そこで生活していたときの不気味な感じが、大人になってもずっと残っているんです。
由尾 小説の帯に「ディストピア大長編」とありますが、村田さんの育ったニュータウンもそんな雰囲気がありますね。ほかにもこの小説は「性」や「性役割」を重要なテーマとしているので、その視点から少しお話しさせてください。空子には家庭内のお手本として母親という存在があり、父親と空子のために自分を犠牲にして働く母親を「肉体がある家電」「人間家電」と呼びます。そして、できるだけ母親のようにならないように生きる術を見つけようとするものの、結局は自分も結婚という枠組みのなかで「人間家電」として生きることを選択するようになる。

このようにジェンダー規範が主題化されていく物語に、重要な存在として登場するのがピョコルンという生物です。パンダとイルカとウサギとアルパカの遺伝子が偶発的に組み合わさったとされるこの生物は、性欲処理や出産、育児など女性が押し付けられてきた性役割を担う存在として描かれます。『世界99』の後半では、ピョコルンがいることを前提とした「友情家族」などの新しい家族のかたちが当たり前になる。
つまり、本作はジェンダーの問題を全面的に提起する小説でもあるのですが、その点について質問が届いています。「『ジェンダー規範』『女性の性役割』『生殖』の問題などについて、村田さんの作品を通して貫くテーマというか、スタンスがあるように感じますが、ご自身では振り返ってどうでしょうか? 『コンビニ人間』を書いた時と、何が変わってなくて、何が変わったと思われますか?」。
村田 私はいつも特にテーマを決めずに書くのですが、デビューしてから現在まで、すべてが繋がっている大きな物語を書いているような気がしています。「生殖」についてもずっと考えています。それはきっと自分自身の経験に基づくものだと思います。子どもの頃、父の実家がある長野県の田舎にお盆に帰省をすると、親族が集まって子どもたちの子宮や精巣の使い道の話をしていました。もちろん直接的な言葉ではないですが、あの子の骨盤は安産型だとか、村田の苗字を残さねばならない、そのためにどうすればいいか、だとか。子どもたちの子宮や遺伝子の使い道は自分じゃなくて大人が決めるんだ、それが当然のことなのだと感じていました。
ピョコルンは私たちに注がれてきた大人のまなざしを引き受ける存在として今回、小説に登場させました。女性の代わりに子どもを産んでくれる。男性の性欲もピョコルンが処理してくれる。ピョコルンがいるからこそ同性婚も複数婚も可能になって、複数人の友達で結婚して子どもを育てるという家族プランも実現する。そんな世界を書いたのは、やはり生殖とは何か、家族とは何かをずっと考えているからだと思います。
幼少期、幼稚園に入る前のころ、私にはなぜ両親が自分と兄を育てなくてはいけないのかよくわかりませんでした。お人よしの夫婦が、自分たちが望んだというより、世界に騙されてそうさせられたのではないかと不安でした。そういう思いが拭えなかったので、もし神様に千人ほど人間を渡されて1万年、世界を保たせろと言われたらどうするか、というような想像を繰り返しするようになりました。幸福な物語になるのではないか、と思うのですが、小説を書き終えると『殺人出産』も『消滅世界』も今回の『世界99』も、なぜか不穏さがあって。特に今回は、ほかの作品より恐ろしい光景が現れた感じがしました。なぜなんでしょうね(笑)。実験なので決して結果を誘導しないのですが、不思議です。

孤独が自分を作っている
辛島 最後にあと二つほど質問を紹介したいと思います。一つ目の質問は、小説に出てくる登場人物の名前について。「村田さんは小説を書きはじめるときに、まず登場人物の似顔絵を描いてイメージを固めると聞いたことがありますが、名前はその段階で決まっているのでしょうか。また、今回の連載では、途中で登場人物の名前を変更したくなったことはありますか」。
村田 ご質問にあったように私はいつも登場人物の似顔絵を描くのですが、そのときにだいたい名前も決めます。名前がないとどのような人物なのか思い浮かべにくいので。苗字は私なりにリアリズムを追求し、千葉に住んでいる人物は千葉に多い苗字を漁ったりしながら選んでいます。でも変わった名前を使いたくなることもあり、たとえばある短編で「虫生」という苗字の人物を出しましたが、あれは古いバイト先の副店長の名前でした。副店長の顔が自分の記憶から消えたら使おうとずっと考えていたので、そのタイミングで名前をお借りしました。
途中で名前が変わることはよくあります。書きながらイメージが変わると、名前も別のものに自然と変わります。『世界99』を連載する前の段階で、何度か名前を変えた人物もいました。あと、今回、ラロロリン人という人種を出しましたが、ラ行ばかりの名前なのは書評家の江南亜美子さんに「村田さんの造語は『パピプペポ』が多いですね」と言われたからです。自分では意識していなかったのでとても恥ずかしく、今度はラ行にしてみました。でもこないだお会いしたときに、ラ行もよく使いますよと言われました(笑)。
由尾 『消滅世界』の主人公は雨音ですが、やっぱり雨のイメージがご自身のなかにあるのでしょうか?
村田 プロとしてお恥ずかしいことですが、覚えていないんです。ただ、左右対称にしたいとか、静かな表情の名前がいいとか、そういうことを考えていた気がします。
辛島 空子は結婚をして苗字が「如月」から「月城」に変わるけど、月は残る。ここらへんも工夫されているなと。主人公以外の人物名も書く前にいろいろ考えて決めたのでしょうか?
村田 空子はさすがに一生懸命考えた気はするんですが、ほかの人物は雰囲気で決めました(笑)。幼少期からなんですが、響きだとか、文字の佇まいとかをばーっとノートに書いていって見比べて、一番違和感がないものにするんです。あとは赤ちゃんのお名前事典のようなものを買い、それで付けていたこともあります。恥ずかしいですけれど。
辛島 みなさんあまり深読みしないでください(笑)。
村田 むしろしていただけると、あたかも賢そうに見えるのでありがたいです(笑)。
由尾 では、本日最後の質問です。「喜怒哀楽、もしくはそのほかの感情でご自身の根源にある感情はなんですか? ちなみに私は「寂」です」。
村田 私も質問者さんと同じかもしれません。家や学校、どこにいても孤独が自分の感情の根っこにある感じがしていました。小説を書いたのも、孤独がエネルギーとなったからです。小説を書くのが小学生のころからちょっと偏愛的に好きだったのも当時の私が孤独だからで、孤独が自分を作っている、自分の世界を広げているという自覚はあります。
辛島 そろそろお時間が参りました。90分が過ぎるとこの壇上が逆さまにひっくり返ってしまうようなので、今日のイベントはこのへんで幕を閉じたいと思います。
村田 小説を出した直後にもかかわらず、とてもたくさんの人とお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。