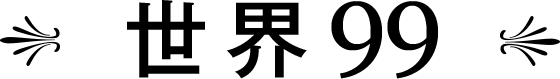トークイベント「村田沙耶香の〈世界〉」【前編】
こちらの記事は前編です。
登壇者:村田沙耶香(『世界99』著者/作家)、辛島デイヴィッド(作家/翻訳家)、由尾瞳(早稲田大学文学学術院教授)
構成/長瀬海
世界で読まれる村田沙耶香

辛島 みなさん、こんばんは。村田沙耶香さんの『世界99』刊行記念イベント「村田沙耶香の『世界』」へようこそ。今日は会場にお越しいただいた読者のみなさんからの質問を組み込みながら、村田作品の世界での読まれ方と、新刊『世界99』をめぐるお話を村田さんご本人にうかがっていきたいと思います。『世界99』は、発売直後に重版がかかるほど大きな反響を呼んでいるそうですね。
村田 読んで苦しさを感じる方も少なくない小説だと思いますが、多くの方の手に渡っていると聞いて、ありがたい気持ちでいっぱいです。
辛島 僕は一気に読みました。主人公のいる世界に苦しさを感じることももちろんありましたけど、とても面白かったです。この長編は『すばる』で2020年11月号から2024年6月号まで、約3年半にわたって連載されていました。初めての連載だと聞いて意外な気がしたのですが。
村田 そうなんです、いつも一挙掲載か書き下ろしでしたから。毎月書けるのだろうかと不安だったので事前にしっかり準備をした上で連載をはじめたのですが、いつまで経っても終わりが見えず、編集者さんにじわじわ追われながら書いていました。
辛島 最初はどれくらいの長さになる予定だったんですか?
村田 長さは決めずに自由に書いていいと言われていました。ただ、最初は1年くらいの連載をイメージしていたものですから、想定の3倍ほどかかったことになります。集英社の2階の廊下にテーブルがあるのですが、そこに通わせていただき、缶詰状態になりながら書いていました。ラストが見えたと思ったところで連載をはじめたのですが、ぜんぜん違う方向に行ってしまい、なんだか申しわけない気持ちになりました。
辛島 村田さんの小説が世界各国で読まれていることはみなさんご存じだと思います。2016年に『コンビニ人間』で芥川賞を受賞された翌年にドイツ語版と英訳が出て、それぞれの国でベストセラーとなりました。この小説が翻訳され、海外の読者に受け入れられることは意識していましたか?
村田 2014年に『GRANTA JAPAN with 早稲田文学 01』に発表した短編「清潔な結婚」を英語に翻訳していただいたことはありました。でも、日本のコンビニを舞台にしたあの小説が翻訳されて海外の人に読まれることは想像してなかったです。
辛島 「清潔な結婚」も『コンビニ人間』も、英訳は翻訳者の竹森ジニーさんが手がけられていますね。村田さんの作品が海外でどのように読まれているのかを綴ったジニーさんのエッセイ「『本当の本当』を探す旅」が『すばる』4月号に掲載されているので、関心のある方はぜひ読んでみてください。
タイトルはどう翻訳されるのか
辛島 『コンビニ人間』は翻訳後にタイトルが少し変更されました。たとえば、英訳ではConvenience Store Womanとなっています。日本語に訳し直すなら「コンビニの女」でしょうか。日本語のタイトルとニュアンスが微妙に違いますね。『すばる』4月号にはイタリア語の翻訳者ジャンルーカ・コーチさんのエッセイも掲載されていますが、それによるとイタリア語版のタイトルは「コンビニの女の子」を意味するLa ragazza del convenience storeのようです。「人間」からWomanに変わったことについて、村田さんはどう思われますか?
村田 私は初めて英訳していただいたときから「文化に任せる」という感覚が強く、タイトルについても「コンビニエンスストア自体がわかりにくい言葉である」とお聞きし、なるほど、と思ってからはそれほど違和感がなかったのですが、読者の方からなぜWomanなのでしょうと聞かれることがよくあります。コーチさんは、イタリア語には男性名詞と女性名詞があるから、どのワードを選んでも性別を無くすことができないとおっしゃっていました。オンラインで翻訳者さんと座談会をしたときには、みなさん、タイトルをどう訳せばいいか葛藤されているとお話しされていて……。英訳版に関しては最終決定権は出版社さんにあるそうで、ジニーさんではなく、編集者さんが決めたようです。
由尾 私は以前アメリカの大学で日本文学を教えていましたが、少し前までは日本の現代作家といえば、村上春樹や吉本ばなな以外はあまり知られていませんでした。若い世代の新しい声がなかなか翻訳されにくい状況が続いていたんです。そんななか『コンビニ人間』が翻訳刊行されると一気にベストセラーとなりました。日本文学の翻訳事情を一気に変えた作品であると言っても過言ではありません。カバーもインパクトがありますし、タイトルも魅力的ですよね。
実は、研究者のなかには、タイトルの「Woman」という表現を問題視する人もいます。恵子が「女性」という性役割を超えて、ロボット人間として生活し、生き延びることが、この小説の中核となっているからです。でも、私はこのタイトルだからこそ世界的なベストセラーになったという側面もあると思っています。各国版の表紙に関しても、いろいろツッコミどころはありますが(笑)、同じことが言えるかもしれません。女の子のかたちをしたかわいいおにぎりの写真やお寿司など食べ物のイラストが有名ですよね。一方で、中国語版は原書のデザインをベースにしています。村田さんからカバーデザインに関して何か希望を伝えたりすることはありますか?
村田 私が何かを言うことはありません。基本的にほぼぜんぶ出版社さんと装幀家さんにお任せしています。私自身に表紙のセンスがあるわけではないですし。ただ、印象的だったのはドイツ語に翻訳されたときのことです。ドイツ語版は表紙がフグなんです。私は特に何も思わなかったのですが、文藝春秋の版権部門の方が、なぜフグなのか気にしていて……。問い合わせたところ、ドイツの出版社さんから恵子は毒があり孤独だからというお返事をいただいたそうです。なるほど、恵子はフグだったのか……と思いました。

『コンビニ人間』のさまざまな表紙
辛島 『世界99』の連載をされている間に、村田さんは世界をあちこち旅されていましたね。インスタグラムにはその時々に撮った写真がたくさんアップされています。今日は写真を通して村田さんが訪れた世界を一緒に旅しながら、『世界99』の小説へと入っていきたいと思います。
まずはロンドンの老舗書店「フォイルズ」の写真です。こちらの本屋さんでは大々的に『コンビニ人間』のプロモーションが展開されていました。写真には、英訳版が高く積まれ、カバーデザインでもある恵子の名札がフィーチャーされている大きなウィンドウディスプレイの様子が写っています。なかなか迫力がありますね。
村田 これは実際に現地で見たわけじゃないのですが、送っていただいた写真を見てすごく感動したので載せました。本屋さんのウィンドウディスプレイに使っていただきほんとうに嬉しかったですし、ウィンドウディスプレイ文化自体にも感動しました。日本ではデパートか、せいぜい玩具屋さんというイメージが強かったので、いろんな本屋さんにあって感動しました。
辛島 ペーパーバック版『コンビニ人間』は色違いの表紙が出ていますよね。
村田 はい。ペーパーバックが出るときに、表紙は黄色とピンクと青の三つのバージョンを出しますと衝撃的な連絡をいただきました。今はそこに紫が加わったそうです。
由尾 英語の本のカバーにはblurbといって、推薦コメントが書かれることがあります。日本の帯文のようなものですね。英訳版『コンビニ人間』のハードカバーには小説家のルース・オゼキさんの「Quirky, deadpan, poignant, and quietly profound」(風変わりで、とぼけたユーモアがあり、心を打ち、静かに深淵をのぞかせる)という言葉が引かれています。ペーパーバック版には「a celebration of non-conformity」と書かれ、「規範」からの逸脱を肯定する作品であることが強調されている。これらは『世界99』にもつながるキーワードですね。 『コンビニ人間』の英訳が刊行された直後、「ニューヨーク・タイムズ」に掲載された村田さんのプロフィール記事が話題になりました。Motoko Richさんが書かれた記事で、セブンイレブンの前で村田さんがたたずんでいる写真が使われていましたが、トルコ語版の表紙はなんとその写真をもとにしたようなデザインになっています。顔が消されていたり、赤いネッカチーフが着けられていたりと多少変化が加えられているのですが、イラストの上に大きくSayaka Murataと書かれていて、作者と小説の主人公をイコールで結びつけようとするかのようです。村田さんは主人公と作者が重ねて読まれることについてはどう思われますか?
村田 確かにあの表紙を見たときはあの写真の自分と同じ洋服とポーズだなと感じたのですが、自意識過剰かも知れないと思って、何も言いませんでした。ほかにも私と恵子を重ねるような読み方をされている国はあるようです。以前、ほかの国の翻訳者さんが私のもとを訪ねて来たときに、翻訳書に「これはサヤカ自身の体験を書いた自伝である」と書かれていると教えてくれました。びっくりしたし、翻訳者さんも、「間違っていますよね、やっぱり」と笑っていて、うまく言えないけれど、誤解や思い込みが悪気なく広まっていく感じは、海外の作家さんが日本での自著の紹介のされかたを見ても似た現象を発見することがあるのかなあ、と想像して興味深かったです。

世界で『コンビニ人間』はどう読まれたか
辛島 イギリス版も面白いですね。初版のblurbには、川上弘美さんとトルコ出身で英語で小説を書くエリフ・バトゥマンのコメントが載っています。どちらも「made me laugh(笑った)」や「Hilarious(愉快)」といった言葉で評していて、『コンビニ人間』の「ユーモア」の部分が強調されていますね。 ちょうどその点に関して、お客さんから質問が来ています。「おそらく笑いを狙って書いたのではない、冷静に物事を客観的に見て滑稽に伝わる書き方がされているように感じました。村田さんご自身は書いているときにニヤニヤ笑ってしまうことはありますか」ということですが、どうでしょうか?
村田 私は自分と小説家の村田沙耶香をわざと乖離させながら書いています。幽体離脱をしている感覚といいますか。小説家の村田さんは人間の村田と違い、感情を持っていなくて、水槽で起きたことを真剣にメモするようにして淡々と実験し、小説を書いているんです。ゲラとして活字化されたものを見ると、あまりに変なことが書かれているのに気づき、笑うというか、不安になることはたまにあります。
辛島 『コンビニ人間』にユーモアを読み取るというのは世界では一般的な読み方なのでしょうか。由尾さんはボストンに2年間いらっしゃって、半年前に帰ってきましたよね。ボストンでは『コンビニ人間』のブッククラブを開かれたとうかがったのですが、みなさんどういう読み方をされていましたか?
由尾 アメリカでは仕事仲間や友人同士で集まり、定期的にブッククラブを開くことが流行っています。日本の読書会のようなものでしょうか。私もボストンで知り合ったある年配の女性に誘われて、何度かブッククラブに参加しました。そこに集まった女性たちは、みな揃ってものすごいキャリアを積んだ弁護士で、今では仕事をリタイアして、数ヶ月に一度食事会を開いて小説の話をすることを楽しみにしている方々でした。彼女たちに日本の小説を読んでみたいと言われ、『コンビニ人間』を選んだというわけです。
面白かったのは、彼女たちとアメリカの大学生たちのリアクションの違いです。学部生と一緒に読んでいると、それこそユーモアや爽快さを読み取るような感想や、現代の日本社会を批判する作品として解釈することが多かったのですが、元弁護士である彼女たちからは、社会的サポートの側面から正義感に溢れた感想や質問が飛び交っていました。どうやったら恵子のような人間に法的サポートを与えることができるか、日本とアメリカではどう違うのか、白羽のような人間はどう救えばよいのかなど、私も聞いていて勉強になりました。
あと、恵子を「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」の観点から精神分析するような読み方が多くありました。海外では精神医学的な文脈で物事を解釈する傾向があるので、村田さんご自身もそのような感想を耳にされたことがあるのではないでしょうか。もちろん読み方は一つではないですし、正しい読みなど存在しないと思うので、どんな意見があってもいいとは私は思っています。村田さんもよく、小説は一度作者の手を離れたら、読者の解釈に委ねられるものだとおっしゃっていますよね。
村田 はい、そうですね。私に小説の書き方を教えてくれた宮原昭夫先生は、作家が書いているのは楽譜に過ぎず、読者がそれを演奏して初めて音楽になるんだとおっしゃっていました。私も、自分だけの力で音楽が完成しているとは思いません。それぞれの人のなかで演奏されるからこそ、違う音色となって響くのだろうといつも考えています。
由尾 読者の方とお話しして、驚いたことはありますか?
村田 よくあると感じます。作品と読者さん個人の化学変化は何万通りもあると思いますし、同じ読み手でも時代が変わって変化することもあると感じています。翻訳されたばかりのとき、海外のどの文学祭に行っても、恵子に対して具体的な診断のある人物であると感じ、作者である村田さんも当事者なのですか、という質問を必ずされるのでそれにも驚きました。ほかにも、すごくびっくりする言葉を頂戴することはありますが、基本的に興味深く感じています。

文学フェスティバルでの出会い
辛島 村田さんは海外の文学祭にたくさん参加されています。インスタグラムには訪れた先々で撮られた写真がアップされていて、眺めているだけでこちらも楽しくなります。イギリスのチェルトナムの写真は、世界で一番古いとされる文芸祭に参加されたときものですね。
村田 はい、竹森ジニーさんと一緒に行ったのですが、とにかく街が温かくて。文学祭も大小さまざまなテントがあちこちに張られていて、とても感動しました。私は英語がぜんぜんできないのですが、それでもほかの作家さんや翻訳者さんと会話ができて楽しかったです。
辛島 海外旅行は得意なんですか?
村田 それが全くダメなんです。一人で海外旅行をすることは一生無理だと思っていました。友達からも来世で頑張ってねと言われていました(笑)。ですが、文学祭に参加してみたところ、こんなに楽しいんだと新しい発見がありました。トロントの文学祭でも一緒に登壇した海外の詩人の方に、明日朝ごはんを食べましょうよ、と提案していただき、壇上では言えないようなお話をすることができて、稀有な時間を過ごせました。ふだんは日本にお住まいじゃない翻訳者さんたちと会えるのも嬉しいです。何度も呼んでくださったおかげで、今はなんとか一人で海外に行けるようになりつつあります。
辛島 マンチェスターで2019年に開催された「Studio Créole」という他国の作家さんとコラボレーションをするイベントの写真もありますね。ここでは日本でも去年『とるに足りない細部』(河出書房新社)が刊行され話題となったパレスチナ出身の作家、アダニーヤ・シブリーさんと交流されたと聞きました。
村田 はい、マンチェスター・インターナショナル・フェスティバルは文学祭ではなく、アート全般を対象としたフェスティバルでした。「Studio Créole」はその中のイギリスの作家さんが企画なさったイベントで、自分の母国語が英語であるという特権についてずっと考えていたことから始まったとお聞きしました。オーディエンスは、7人の作家が母国語で朗読するのを聞きながら、骨伝導のヘッドホンをつけて、ステージの真ん中で同じタイミングで俳優さん演じる英訳のパフォーマンスも同時に体験する、という、私にとってはかなり心惹かれる企画で、不思議な時間を味わえました。 ただ、私は英語が全くできないのでマンチェスターの人たちが困惑してて。そんな私をアダニーヤさんが優しく助けてくれたんです。ゆっくりとした英語でしゃべりかけてくれたり、毎日メールで連絡をくれたりして、とても親切にしていただきました。一緒にデビッド・リンチの絵の個展を見に行ったのもいい思い出です。おろおろしていた私と仲良くしてくださったアダニーヤさんにはたいへん感謝しています。