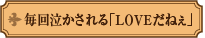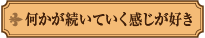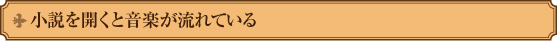
小路 倉科さんはかなりの読書家で、僕の本も結構読んでくださっているとお聞きしたんですが。
倉科 ええ、以前から小路さんの小説のファンで、家に一番あるのは小路さんの本なんです。空シリーズというか、『空を見上げる古い歌を口ずさむ』や『高く遠く空へ歌ううた』『空へ向かう花』とか、『HEARTBEAT』。今回新作が加わった「東京バンドワゴンシリーズ」も大好きで、飛び飛びですが愛読しています。
何か大事件が起こるわけではないのに、日常の小さな事件をみんなが寄り集まってハートフルに解決していく。それがすごく身近に感じられて、愛おしくなるような小説ですね。
小路 それはありがとうございます。
倉科 今回、小路さんと対談できるとお聞きして、ああうれしいと思って、改めて小路さんの小説の魅力って何だろう、私は何が好きなんだろうって考えてみたんです。内容も語り口もすべて好きなんですけど、たとえば小路さんの小説には常に音楽が流れている気がするんです。私は本を感覚で読むところがあるので、行間に音楽が流れている感じって、すごく心地いい……。
小路 一番最初に僕の本を手にとったのは、そういう直感ですか。
倉科 ええ。あ、面白そうという勘です。
小路 本屋さんで?
倉科 いえ、図書館です。その頃私は中学生か高校生で、まだ自分が自由に使えるお金があまりなかったので、図書館に通って本を読んでいたんです。それで小路さんの本を読んだらすごく面白くて、シリーズがあると聞いて、どんどん読み始めたんですね。
図書館で読んだ本でも大人になって自分の好きな本はどうしても手元に置いておきたくて、今、小路さんの本を少しずつ集めているんです。
小路 それはうれしいな。でも、倉科さんが本を好きになったきっかけって何かあるんですか。
倉科 子供の頃から活発に外で遊ぶタイプで、読書とはかけ離れていたんですけど、中学生のときに図書館で本を読んでみたら、どこか別の世界にタイムスリップできたんですね。現実と離れて違う世界に行ける。そういう体験をしてから本が大好きになったんです。
小路 その本、覚えています?
倉科 確か、森絵都さんの『カラフル』だったと思うんですが。
小路 へえ、『カラフル』から本好きになったんだ。

倉科 今は職業柄、台本ばかり読んでいるので、ちょっと読書から離れるときもありますけれど。
小路 僕には全然経験ないから聞くんだけど、台本読むのと小説読むのと、感覚の違いってありますか。
倉科 そうですね。小説だと現実に起き得ないことも頭の中で再現できるけど、台本を読むときには、映像として現実に存在させなければいけないので、うまくいえないけど、ちょっと違うんですね。
小路 役者さんって結局「物語」を演じるわけですよね。だから自分が演じる物語の脚本を読むときの気持ちと、普通に小説を楽しむときの気持ちの感覚の違いって何なのかなと。書き手として、以前そのことを不思議に思ったことがあって、聞いてみたんですけど。
倉科 小説は、わあ面白いとか、つまんないとか、単純に読者として外側から楽しめるわけですが、脚本の場合は深く中に入り込まないといけないですからね。とくに自分が演じる役は、このト書きはどう演じればいいのかと書いてないところも想像しないといけないし。
小路 わかります。ト書きには状況説明があるだけで、これから演じる人の人生が全部書いてあるわけじゃないですからね。でも演じるときはその人が今まで生きてきたすべての物事を自分なりに考えなければいけない。お互い文字を読んで想像すること自体は一緒だけれど、そこが大きな違いですね。
倉科 そう、その埋めていく作業が大変ですね。私はまだ駆け出しだからいろいろ試していますが、役が決まったら、ずーっとその役柄の背景を考えていますね。そこをちゃんと埋めておかないと、体も気持ちも動かないし。現場では考えている暇はないですからね。
でも私、ずーっと書き続ける作業も大変だと思うんです。これはぜひ今日お聞きしようと思ってきたんですが、小路さんはどうして作家になろうと思われたんですか?
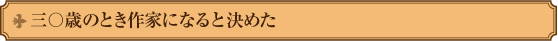
小路 僕はね、三〇歳の誕生日に作家になろうと決めたんですよ。
倉科 えっ、そうなんですか。それまでは別のお仕事をされてたんですよね。
小路 広告業界でプランナーとかコピーライターをやっていて。
倉科 文章を書くお仕事ではあったんですね。
 小路 そう、一応書く仕事ではあったんだけど、二四歳のときに広告業界に入って六年経って、このままでいいのかって考えたんです。男って三〇になると考えるんですよ。僕、もともとミュージシャンになりたかったんですね。中学のときからバンドを組んでいて、ずっと音楽をやっていて、絶対ミュージシャンになるんだと思っていたんだけど、二〇歳くらいのときに才能がないということに気づいて、あきらめた。それで広告業界に入ったんですが、ポスターやCMを作っていてもそれは共同作業じゃないですか。みんなの作品であって、俺のじゃない。「自分のもの」が作りたいという気持ちがずっとあって。それで三〇歳のときに、じゃあ自分は何になれるんだろうと考えて、作家しかない、作家になろうと決めて書き始めたんです。
小路 そう、一応書く仕事ではあったんだけど、二四歳のときに広告業界に入って六年経って、このままでいいのかって考えたんです。男って三〇になると考えるんですよ。僕、もともとミュージシャンになりたかったんですね。中学のときからバンドを組んでいて、ずっと音楽をやっていて、絶対ミュージシャンになるんだと思っていたんだけど、二〇歳くらいのときに才能がないということに気づいて、あきらめた。それで広告業界に入ったんですが、ポスターやCMを作っていてもそれは共同作業じゃないですか。みんなの作品であって、俺のじゃない。「自分のもの」が作りたいという気持ちがずっとあって。それで三〇歳のときに、じゃあ自分は何になれるんだろうと考えて、作家しかない、作家になろうと決めて書き始めたんです。
倉科 へえー、なろうと決めて作家になって、書こうと決めて書いた。すごい。
小路 そうそう、わりと形から入るタイプ(笑)。形から入って、作家になれちゃったから不思議。倉科さんが女優になったきっかけはオーディションでしょう?
倉科 はい、そうです。
小路 ご実家は熊本ですよね。東京のオーディションを受けようと思ったのは、どうしてですか。
倉科 冒険してみようと思ったんです。もともと私は現実的な子供で、長女だから高校卒業したら、固定給の安定した仕事についてお母さんを楽させてあげたいと思っていたんです。でも、今の小路さんのお話と似てますが、あるとき、私の人生それでいいのか、それじゃつまらないなという思いが大きくなって。まだ自分が見ていないものを見たくって、冒険してみようと。
小路 なるほど。倉科さんはきょうだいがいっぱいいる大家族だそうですね。
倉科 そうなんです。妹が三人、弟が一人で、私が長女。小路さんの「東京バンドワゴンシリーズ」の堀田家も大家族でしょう。だから読んでいると懐かしくて。
小路 一番人数の多い最盛期で一つの家で何人暮らしていたんですか?
倉科 ええと、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、お父さん、私、妹たちと弟の九人。それに家がブリーダーをやっていたので、多いときで犬が二〇匹(笑)。
小路 わあ、九人と二〇匹! じゃあ朝ごはんのときなんか本当にたくさんいて、わいわいがやがや賑やかだったでしょう。
倉科 そう、堀田家の家訓は「食事は家族揃って賑やかに行うべし」ですよね。うちも全員揃って食べてましたから、本当に似てるんです。「東京バンドワゴン」の堀田家の人々が賑やかに会話している風景ってすごく素敵ですよね。私、小説でよくこんな会話の仕方を表現できるなと感動しながら読んでいるんですが。
小路 あの会話部分ね。最初はあの会話に一応地の文章も入れていたんですよ。会話だけじゃなく、誰が言った、誰がどうしたっていう文章を挟み込んでいたの。でも、それをやるのが邪魔くさくて(笑)。
倉科 とにかく大勢過ぎますからね。
小路 それでついに、会話だけにしちゃった。「東京バンドワゴン」はホームドラマを書こうと思ったのだから、ドラマなら台詞だけでいいじゃんと思ってね。最初の一作を書いたときはシリーズになるなんて思ってなかったので、考えなしにそうしてしまったのが、それから七年このシリーズが続くことになって。正直言えば、毎回あの会話のところを書くのが大変で大変で。このシリーズで一番苦労しているところかもしれない(笑)。
倉科 あの会話の場面が素敵なのは、地の文の説明がなくても誰が言っているのかということがすっと入ってくるからなんですね。それだけ堀田家の一人一人のキャラがしっかりしているから、誰が話しているのか自然に頭に浮かんでくるんだと思う。
小路 ありがとうございます。そう言っていただけると苦労の甲斐がある(笑)。
倉科 あの会話を読んでいると、自分がすごく懐かしい場所に帰ってきたような気持ちになれます。設定が下町の古書店ということもあるんでしょうが、この懐かしい感じは、「東京バンドワゴン」だけじゃなく、小路さんのほかの小説にも私はいつも感じるんです。
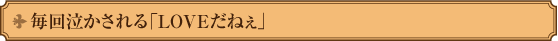
小路 堀田家で倉科さんが一番好きなキャラは誰ですか?
 倉科 勘一おじいさん。江戸っ子の「てやんでぇ」って感じが好き。何か事件が起きると探偵よろしく解決に乗り出していくあのアクティブさがいいですよね。こういう方って今本当に少なくなりましたし、時代もどんどん変わっていくわけですが、この小説を読んでいると、変わらないものもあるんだなあって思える。うちも大家族で、そんなに裕福ではないけれど、それはそれですごく幸せだったなという思いもあるので。そういう感覚が堀田家にもあるのかなと想像しながら読んでいるんですけど。
倉科 勘一おじいさん。江戸っ子の「てやんでぇ」って感じが好き。何か事件が起きると探偵よろしく解決に乗り出していくあのアクティブさがいいですよね。こういう方って今本当に少なくなりましたし、時代もどんどん変わっていくわけですが、この小説を読んでいると、変わらないものもあるんだなあって思える。うちも大家族で、そんなに裕福ではないけれど、それはそれですごく幸せだったなという思いもあるので。そういう感覚が堀田家にもあるのかなと想像しながら読んでいるんですけど。
あと、伝説のロックンローラー我南人も素敵ですよね。あの毎回出てくる「LOVEだねぇ」っていう決め台詞には、いつも泣いちゃいますもの。
小路 ほんと? 不思議なのはこのシリーズを読んでくださった読者の方は、みんな我南人が大好きだって言ってくださるんです。僕の中ではこの小説の主人公は一応今八三歳の勘一だったんですが、いつのまにか我南人のほうが人気が出ちゃった(笑)。
倉科 やっぱり我南人の「LOVEだねぇ」の台詞が効いているんですよ。あの台詞はどうやって出てきたんですか?
小路 たぶん忌野清志郎さんの「愛しあってるかーい」っていうのが頭にあって、それが「LOVEだねぇ」になったと思うんですよ。でもこの台詞は一作あたり一回か二回くらいしか言ってないのに、何か我南人のキャッチフレーズみたいになっちゃいましたね。
倉科 意味わからないところで突然我南人が「LOVEだねぇ」って言う。そこに語り手のサチおばあちゃんが「意味わかんないけど」って突っ込む場面もすごく私は好きなんです。
このサチおばあちゃんはもう亡くなっていて幽霊なんですけど、語り口がとてもやわらかで優しい気持ちになりますね。サチおばあちゃんのことは、孫の紺とその息子の研人にしか見えないという設定も好きです。
小路 幽霊が語り手だとどこでもすぐ行けて何かと都合がいい(笑)。

倉科 あと舞台が古書店というのもすごく気に入ってます。私、古本屋が大好きなんです。
小路 へえ、古本屋に行くんですか?
倉科 よく行きます。古本屋の雰囲気が好きなんですよ。普通の書店にはない、何か哀愁漂う特別な空気がある。誰かが読んだ本をまた見ず知らずの人が手にとって読んでいるということも、私はいいなと思えるんです。何かが続いていく感じがすごく好き。
「東京バンドワゴン」には古書店らしく、古本の専門知識も結構出てくるので、それを読むのも楽しみです。
小路 適当な知識なので、嘘も混じってます。ごめんなさい(笑)。
倉科 いえいえ。ところで新作の『レディ・マドンナ』はどんな作品なんですか? 今からすごく楽しみなんですが。
小路 前回の『オブ・ラ・ディ オブ・ラ・ダ』では、かなり大きな事件が起きて振幅の激しい一冊になったので、今回はまたいつものテイストに戻したんです。
堀田家には女性がいっぱいいるので、今回は彼女たちに活躍してもらおうかなと思って。それでタイトルを考えてたら、“おおビートルズの「レディ・マドンナ」があるじゃないか”と思いついて、これに決定したんです。
倉科 女性たちが活躍するんですね。読むのが楽しみだな。
小路 本ができたら送りますよ。
倉科 ありがとうございます。でも小路さんの本は少しずつ自分で買って本棚に増やしていくっていうのが幸せなんですよ。愛おしくて素敵な物語をこれからも書き続けてください。