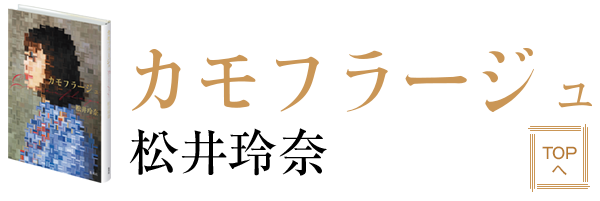インタビュー誰もが何かを装っている、
その化けの皮がはがれたところを書きたかった
このたび松井さんが初めて書いた短編集『カモフラージュ』が刊行されました。収録されているのは、さまざまな年齢、性別の人々が登場する六つの物語。いずれも着想の面白さと、たしかな文章力が感じられます。恋愛小説からホラー小説まで、それぞれの作品はどのように生まれたのか。これまでの読書遍歴は?「作家・松井玲奈」のインタビューをお届けします。
聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=神藤剛
「活字がないと無理!」なときがある
──『カモフラージュ』を読んで、本をよく読まれている方だと感じました。これまでの読書体験を教えてください。
子どもの頃に一番好きだったのは『ハリー・ポッター』シリーズです。それに「青い鳥文庫」が好きで、とくにミステリ作品をよく読んでいました。十代後半からはアイドルの仕事を始めたので本を読む時間がなくなってしまったんですが、それでも定期的に「活字がないと無理!」みたいなときがあって、仕事の合間に読んだりはしていました。ただ、そのときは軽いものを読む程度でした。集中して読むようになったのは、三年前に島本理生さんの『よだかの片想い』を読んでから。すごく面白くて、次の日に本屋さんに行って、店頭にあった島本さんの本を全部買って読み始めたくらいです。島本さんの作品が私を読書に引き戻してくれたんです。
──松井さんは島本理生さんの『リトル・バイ・リトル』の文庫解説を書かれていましたね。自分でも小説を書こうと思われたのにはきっかけがあったんですか?
書評やエッセイを書く機会がけっこうあって、周りから書けると思われたみたいで、ファンクラブの会報誌にショートショートを書くように勧められたんです。その作品がきっかけで、「小説すばる」さんから短篇を書いてみないかとお話をいただきました。
──それが『カモフラージュ』の最後に収録された「拭っても、拭っても」ですね。初めて小説を書いてみてどうでしたか。
もともと文章を書くのが好きで、書いていないとエネルギーが内側にたまっていくようで苦しくなることがあります。だから、小説を書くことは、エネルギーの新しい発散法をもらったような気がしましたね。
──最初の短篇を発表してから半年足らずで単行本が出るのは速いペースだと思うのですが、そのエネルギーゆえですね。ここからは『カモフラージュ』に収録された短篇について収録順にお聞きしていきます。まず「ハンドメイド」。恋に悩む二十四歳の女性が主人公です。ある事情でホテルでしか会えない関係のゆえ、彼のために作ったお弁当をホテルに持っていく場面が印象的です。
ホテルの部屋を舞台にしたのは、出演していたNHKの『まんぷく』の撮影のために、長いときには週の半分くらい大阪のホテルに泊まっていたからかもしれません。ほかの小説もそうですが、自分の実体験じゃなくても、日常のあれこれをつないでいって、点と点が線になる感じで書いています。
──お忙しいと思うのですが、思いついたことをメモしたりしますか。
普段はしないですね。ただ、「ハンドメイド」のときは例外で、駅の中を歩き回りながら、登場人物に言わせたい台詞をスマホのボイスメモでとったりしていました。客観的に見たら、超気持ち悪い人だなと思います(笑)。パッと思いついたので、とっさに。めったにしないですけど。
女の子には〝旬〞がある
──次の「ジャム」の語り手は小学生です。お父さんが帰宅したら、お父さんに、お父さんと同じ顔をした三人が裸でくっついている、というホラー的な導入部から始まります。
最初に思い浮かんだのが、人が人を吐き出すというイメージでした。そのイメージを書きたい。でも、それって一体何なんだろうって考えたときに、ストレスという言葉が浮かんできました。ストレスを吐き出すイメージです。それを食べ物につなげたとき、ふと、ジャムが出てきたんです。
──ジャムは甘くておいしいですけど、ちょっと見方を変えると気持ち悪い。発見でした。
そうなんです。読む前と読んだ後では、ジャムの見え方が変わるんじゃないかな、と。語り手を小学生にして、無垢(むく)な子どもの恐ろしさみたいなものが出たらいいなと思いながら書いていましたね。
──「ハンドイド」にはお弁当のオムライス。「ジャム」にはジャム。『カモフラージュ』はどの作品にも、食べ物が出てきますね。
どの短篇にも食べること、食を共通させることは意識していました。この話にはこの食べ物、この料理を使おうと考えるのは、難しかったけど楽しくもありましたね。
──「いとうちゃん」は明太子スパゲッティが印象的ですね。太ることを気にしている女の子〝いとうちゃん〞が主人公。メイド喫茶に勤めていますが、メイド喫茶のことを調べたりしたんですか。
自分でも行ったことあったので、そのときの記憶がもとになっています。お金のシステムとか細かいことは、メイド喫茶で働いていた子に教えてもらいました。お店によってだいぶ違うみたいで、奥が深いなと思いました。
──ドキッとしたのが、いとうちゃんがメイド喫茶で働きたくて焦っている場面で「早くしないと女の子である私が死んでしまう」とお母さんに訴えるところです。
その場面は私も好きで、書いているときにはにやにやしてしまいました。自分がアイドルをやっていたからということもあるんですけど、女の子の〝旬〞ってあると思うんです。考え方は人それぞれですけど、脂が乗っているというか、一番かわいい、いい時期を、何もしないまま逃したくないと思っている女の子はたくさんいるんじゃないかなと思いますね。
──そんな時期に太り始めてしまったいとうちゃんがどうなるか。ぜひ読んでほしいですね。そして、「完熟」では一転して大人の夫婦を描いています。まず三十代半ばの男性の一人称で、桃を食べる女の姿がエロチックな思い出として描かれ、次いでその妻の一人称で、夫が自分に向ける熱っぽい視線について書かれています。男性のフェティシズムをテーマに書こうと思われたのはなぜですか。
桃をよく食べていたのが直接のきっかけです。桃を注意深く触るときの感じとか、危うさみたいなものが色っぽいなと思ったんです。男性のフェチということで言うと、知り合いに制服フェチの男性がいて、「大学生になった女の子たちがなぜ〝制服ディズニー〞をするのか」について一時間ぐらい熱く語られたことがあるんですよ。こんなに制服に執着があって、一時間話し続けられるくらい考えている人がいるんだ、フェチって奥深いな、と。女性にもフェチはあるので、執着してしまう気持ちを書いてみたいと思いました。
──フェチな男性と、そのフェチに薄々気づきながら気づかないふりをしている女性。両方から描いていることが興味深かったです。
たまにドラマとかでも、一話目で男性視点で描いて、二話目で女性視点に変わって、三話でその後の話が進んでいく、みたいなことがありますよね。それに近いです。頭の中でスイッチを切り替えながら書いていった感じです。
女優と小説家、影響しあうところ
──続く「リアルタイム・インテンション」はまたがらっと雰囲気が変わって、男性三人が主人公。動画配信をしている彼らが、番組の企画として「本音ダシ鍋」という闇鍋をするお話です。なぜ、動画配信をしているユーチューバーみたいな人たちの話を書こうと思われたんですか。
もともとは大学生の話で、それから男性ボーカルグループにしようかなとかも思ったんですが、いまだったら動画配信かな、と。実際にグループが不仲で解散しちゃったり、出演している人と企画・編集している人とでお金の配分で揉めたりする話を聞いたことがあるので。ユーチューブで謝罪動画とか、炎上している動画を探して参考にしました。
──舞台を思わせるテンポのいい台詞のやりとりが楽しいですね。ワンシチュエーションものですし。
いま書いているのは小説ではなく、戯曲なんじゃないかと不安になりながら書いてました(笑)。書いたものを口に出して読んで、リズムやテンポを調整したりもしましたね。でも、声に出したときのリズムのよさと、文字で見たときのリズムのよさは違う部分もあることに気づきました。それも文章の面白いところだなとか、発見がたくさんある作品でした。
──最後の「拭っても、拭っても」は潔癖症の若い女性が主人公です。それも、元カレからの影響でというところがユニークです。
好きな人ができると服の趣味ががらっと変わっちゃう人っていますよね。人に影響されてやっていることなのに、それが本当の自分だと思い込んでいる人が多いなとつねづね感じていました。とくに女の人は、その人とつき合っていた自分を肯定することで、自分の恋は間違いじゃなかったって思いたいところがあるんですよね。彼に費やした時間は無駄じゃなかったと自分に言い聞かせているというか。
──なるほど。そうした影響を潔癖というかたちで描いているところが生々しいですね。
この話のきっかけは、街でかかとに絆(ばん)創(そう)膏(こう)を貼っている女性を見かけたことなんです。それが私の中ではちょっと許せないというか、自分が男性だったら嫌なんじゃないかと思っちゃったんです。見た目はかわいく装っているのに、絆創膏を貼ったままでいいの? みたいな。そこからさらに、絆創膏を指にしている人が作る料理は何が嫌かという話になっていったんですよね。
──その料理が何なのかは読んでのお楽しみですね。たしかにちょっと嫌でした(笑)。ここまで一作ずつ語っていただきましたが、本としてのタイトルは『カモフラージュ』。これはどうやって決めたんでしょうか。
いくつか案を出して、その中から編集者さんたちと相談して決めました。どの作品にも共通するのが、誰でも何かに対して装っているというか、カモフラージュしている部分があるんじゃないか、ということではないかと。その化けの皮がはがれたところを書きたかったんだなと後で気づきました。
──「装っている」という見方は、松井さんの女優というお仕事とも関連しますね。小説を書くことが女優の仕事にフィードバックされたと感じることはありますか。
台本の読み方が変わりましたね。台詞一言一言に対して、脚本家さんがどう考えてこの台詞をこの役に言わせているんだろう、と以前よりも考えるようになりました。私も小説を書いているとき、この流れの中でこの台詞を絶対に言わせたい! と思って書いているので。
──その逆に、女優の仕事が小説を書くことに影響していることはありますか。
私は小説を書くときに、いつも頭の中に映像を思い浮かべているので、映像のお仕事で監督がやっていることがすごく参考になります。文字だけしか書かれていない脚本をもとに、カット割りをして、どう見せるかを考える、というプロセスを間近で見られるので。自分にはとても監督はできないなと思うんですが、小説なら自分一人でお話を作ることができるし、小説の中で、カット割りや演出をすることもできる。小説を書くって難しいけど面白いなと思います。
「青春と読書」5月号(4月20日発売)より転載